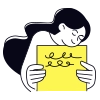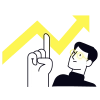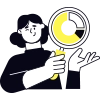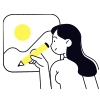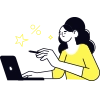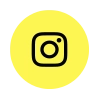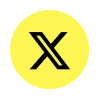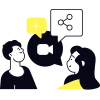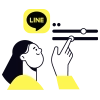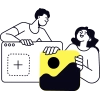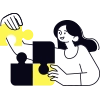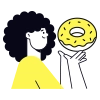視聴されるだけで終わらせない。採用や認知活動につなげる動画運用
TikTokは「単に流行っているSNS」ではなく、今やユーザーが“知る・興味を持つ・選ぶ”までの行動起点となるメディアです。検索エンジンや公式サイトより先に、TikTokでブランドや商品に触れるケースも珍しくありません。
とくにZ世代・若年層との接点づくりにおいて、短尺動画の持つ情報密度と感情伝播力は強く、印象や共感を生むストーリーデザインが求められます。しかし、「動画を出しても再生されない」「撮ってみたけど成果に結びつかない」といった声も多く、継続的な運用設計と改善サイクルがなければ成果にはつながりません。
toritokeでは、戦略設計からコンテンツ企画、撮影サポート、アカウント運用、分析改善まで一貫して支援。
“バズらせる”よりも“届けたい相手に継続的に届く”運用体制を構築します。
TikTok運用とは
TikTokはエンタメやトレンドだけでなく、「情報検索」「ブランド接触」「購買行動」の起点になりつつあるSNSです。検索機能やレコメンド精度が高く、フォロワーに限らず動画内容に反応したユーザーへ表示されるため、適切な構成と初動の設計次第で認知を一気に拡大することも可能です。
さらに、動画に感情が乗りやすい設計になっているため、「印象に残る」「共感する」「シェアしたくなる」といった行動に繋がりやすく、無名の商品でも“体験”として伝えることで興味を引くことができるのがTikTokならではの特徴です。
動画の長さ・構成・音選び・冒頭3秒・コメント欄の活用など、細かい設計ポイントを押さえながら「見られて終わらない」動画づくりが、企業アカウントに求められます。
TikTok運用でよくある悩み
撮影・編集のハードルが高く、始めたくても動けない
TikTokは動画が主軸のプラットフォームであるため、投稿には撮影・編集といった制作工程が必須になります。しかし実際には、「スマホでの撮影に慣れていない」「編集アプリを使いこなせない」「出演に協力してくれる人がいない」などの理由から、企画までは進んでも“初投稿にたどりつけない”というケースが多くあります。
例えば、製造業の企業で製品の製造工程を発信しようとしたが、作業現場での撮影環境や顔出しの可否、誰が話すかなどが決まらず、結果として構想だけで止まってしまった、というような事態はよくあります。
発信のアイデア自体はあっても、実行のハードルを越えられないという現場の声は非常に多く聞かれます。
企業アカウントとして、どのように活用すべきかが定まらない
TikTokはエンタメ寄りの印象が強く、個人クリエイターやインフルエンサーの投稿が目立つ中で、「企業として何を投稿すればよいのか分からない」「自社の目的とTikTokの世界観が合っているのか不安」といった戸惑いの声が多く聞かれます。
特にBtoBやサービス系の業種では、商品や機能の紹介が動画映えしにくく、「社内でやってみたものの反応が得られず、そのまま止まってしまった」というケースがよくあります。
例えば、採用ブランディングを目的にTikTok運用を始めたものの、発信する切り口が定まらず、自己紹介や軽い日常投稿に終始してしまい、目的との乖離が広がっていったという声もあります。TikTokを通じて“何を伝えたいのか”“誰に向けたアカウントなのか”が不明確なまま運用を続けてしまうことで、発信内容がぼやけ、ユーザーにも意図が伝わりにくくなる状況が生まれやすくなります。
撮るだけで満足し、改善されないまま投稿が続いている
動画を出すこと自体が目的になってしまい、「なぜ伸びたのか/伸びなかったのか」を検証せずに次の動画を作ってしまうケースも多くあります。
TikTokでは、再生回数やいいね数に目が向きがちですが、それだけではユーザーの関心や行動を正確に把握することはできません。
例えば、毎週1本投稿している企業アカウントで、実は“ユーザーの離脱が5秒以内に集中していた”にも関わらず、構成を変えずに同じパターンを繰り返していたことで、フォロワーも増えず、エンゲージメントも頭打ちになってしまったという例もあります。
アルゴリズムやトレンドが速すぎて、何が正解か分からない
TikTokは他のSNSに比べてアルゴリズムのアップデートやUIの変更、トレンドの入れ替わりが非常に速く、「昨日までは効果的だった投稿形式が、翌週には通用しない」といったことが頻繁に起こります。
また、音源の人気や投稿の最適時間帯なども日々変化しており、「真似したつもりでも再現できなかった」「急に再生数が半減した」といった声も多く聞かれます。
このスピード感に社内体制が追いつかず、判断が遅れ、手応えのない投稿を続けてしまうことも少なくありま
toritokeのTikTok運用ではこのように解決します
01|目的に合わせた活用方針を定め、アカウント設計から支援
TikTokは「とりあえず動画を出してみる」だけでは成果につながらず、どの層に・どんな印象を残し・どんな行動につなげたいのか、明確な活用方針が必要です。
toritokeでは、まず採用・認知・集客・教育など、企業におけるTikTok活用の目的を明確にし、アカウントの方向性・投稿のトーン・投稿カテゴリの構成まで含めた初期設計を行います。
例えば、「中途採用における若手人材との接点づくり」を目的とした場合、社内の日常や働く姿勢が見える動画を中心に、ハッシュタグやトレンドの取り入れ方も“共感”に寄せた構成にすることで、ブランドイメージの構築と応募動線の強化につながります。
02|撮影・編集の負担を軽減し、無理なく続けられる体制を構築
撮影や編集は、TikTok運用における最初のハードルです。toritokeでは、スマホで撮影可能な構成やセリフのテンプレート化、撮影スケジュールの仕組み化などを通じて、制作工数を最小限に抑えながら継続できる体制を整えます。
編集に関しても、簡易編集アプリの使い方サポートや編集代行の提案を含め、状況に応じた負担分散を支援します。
例えば、投稿本数と制作リソースをあらかじめ整理し、月にまとめて撮影して小分けで投稿する体制にするだけでも、日々の負担感は大きく減らせます。撮影日や役割分担を定型化することで、属人化を防ぎつつ、無理のないルーチンとして社内に定着させやすくなります。
03|再現性のある構成で、感覚頼りにならない動画づくりを支援
TikTokでは「最初の3秒で惹きつける」「縦型画面の中で動きをつける」「視聴完了率を上げる構成にする」といった、動画に適した基本設計が存在します。
毎回構成がばらばらだと、制作の負担が増えるだけでなく、伝えたい内容が視聴中に届かない可能性も高まります。そのため、目的に合った構成テンプレートを用意し、「問いかけ→ビフォー/アフター→行動喚起」など、一定のルールに基づいた設計にすることで、制作効率と伝達力を両立させることができます。
構成を定型化しておけば、誰が関わっても動画の方向性がぶれず、属人化も避けやすくなります。
04|TikTok特有のアルゴリズムとトレンド傾向を踏まえた投稿設計
TikTokでは、フォロワー数よりも“動画そのもの”が評価されるため、投稿単体でアルゴリズムに最適化する必要があります。
toritokeでは、音源のトレンド、投稿時間帯、動画の尺やスタイルの変化など、TikTokの特性に合わせた「今届きやすい構成・企画」を運用中に随時アップデートしていきます。
また、再生数だけでなく“どのユーザーにどう届いたか”のデータ分析をもとに、フォロー/保存/外部リンク遷移など行動指標の変化を確認し、毎月の投稿設計に反映します。
TikTok運用代行サービス概要
TikTokは、エンタメやトレンドだけでなく、「商品を知る」「企業に興味を持つ」「サービスを比較する」といったユーザー行動の起点となるチャネルへと変化しています。
特に若年層においては、検索よりも先にTikTokで情報に触れることも珍しくなく、短尺動画の持つ没入感と情報密度を活かした設計が重要になります。
しかし、ただ動画を出すだけでは成果にはつながりません。どんな目的で、誰に向けて、どんな印象を残し、どんな行動につなげるのか——。アカウントの設計、企画の切り口、構成のルール、撮影と編集の体制まで含めて、あらかじめ戦略的に整えておく必要があります。
TikTok運用代行では、アカウントの初期設計から、動画の企画・撮影・編集・投稿・分析・改善までを一貫して支援。“バズ狙い”ではなく、“届けたい相手に定着する運用”を前提に、企業の目的や体制に合わせた継続的な発信を実現します。
主な支援内容
- 目的・ターゲットに応じたアカウント設計と活用方針の策定
- 動画構成テンプレートの設計(シナリオ台本・セリフの定型化)
- 撮影スケジュール管理、撮影同行または簡易マニュアルの提供
- スマホ編集または編集代行による動画制作
- 投稿の最適タイミング設計と予約投稿(ツール活用可)
- いいね/保存/遷移などの数値分析と改善サイクル構築
- 月次レポートと定例フィードバックの実施
TikTok運用のご相談を無料受付中!
「始めたいけれど、何から決めればいいか分からない」「社内に動画を扱える人材がいない」「投稿はしているが、成果が出ている実感がない」。そんな段階からでも問題ありません。
TikTok運用は、企画や撮影、編集だけでなく、“誰に向けて、どう届け、どんな行動につなげたいのか”という設計が成果を左右します。まずは現在の状況や目的を伺いながら、適切な投稿設計、社内体制、改善サイクルなどについてご提案させていただきます。
- アカウントの方向性や活用目的の整理
- 運用スタイルに応じた撮影・編集体制の構築方法
- 動画の構成テンプレートやテーマ出しの方法
- 数値分析の見方と改善の回し方
- リソース状況に応じた運用分担(社内外の切り分け)
など、「動画のことがよく分からない」状態でも大丈夫です。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。