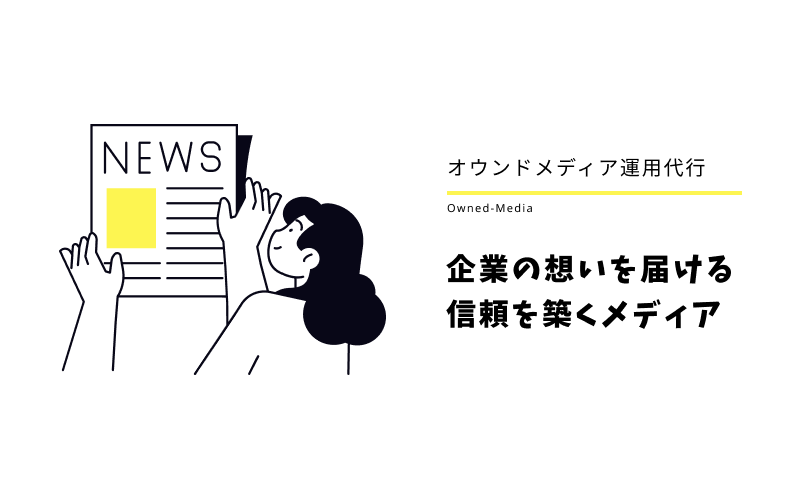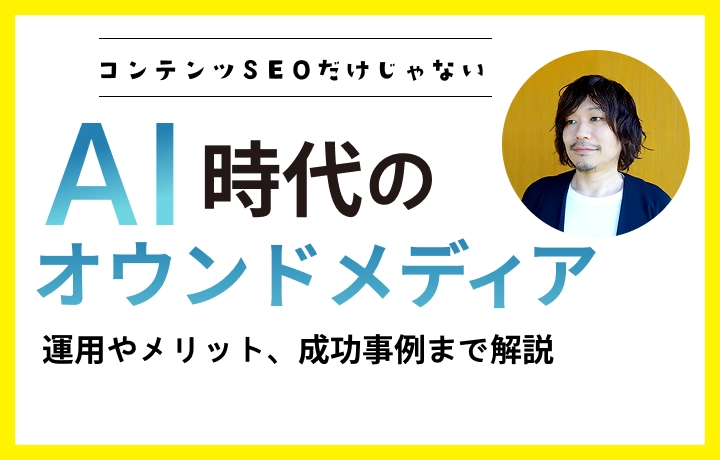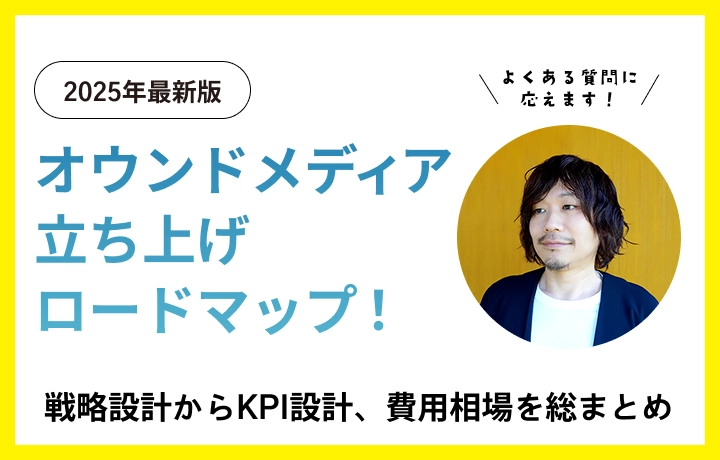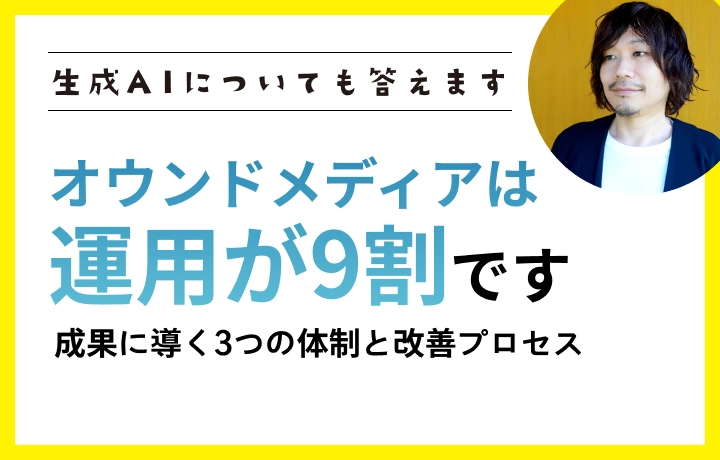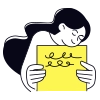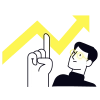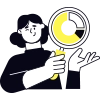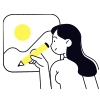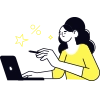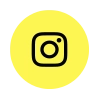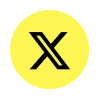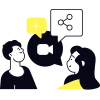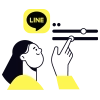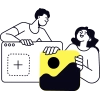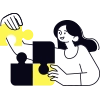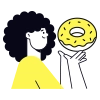顧客との信頼関係を育む“ブランド資産”としての運用を
オウンドメディアは、企業の想いや価値観を言語化し、ユーザーとの信頼関係を育むための大切な媒体です。採用、サービス紹介、社会貢献など、発信したい情報があっても、「どう設計すればいいのか分からない」「書いてはいるけれど、読まれている実感がない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
特に、立ち上げたまま更新が止まっていたり、SEO記事ばかりで本来伝えたいメッセージが埋もれてしまっていたりと、「情報は出しているが、伝わっていない」状態に陥ることもよくあります。
toritokeでは、メディアの目的やターゲットに応じたコンセプト設計から、記事の企画・制作、公開後の効果測定と改善までを一貫して支援。ブランディング、採用広報、リード獲得など、企業のフェーズや戦略に合わせて、意味のある発信をともにつくり上げていきます。
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

オウンドメディアとは
オウンドメディアとは、自社が主体となって運営するWebメディアのことを指します。コーポレートサイトやブログ、特設サイトなどがこれにあたりますが、単なる「情報発信の場」ではなく、企業が伝えたい価値観やビジョンを自社の言葉で伝え、長期的な関係性を築いていくための手段として注目されています。
例えば、採用活動では「会社の空気感や社員の声」を伝える手段として。BtoBのサービスでは「業界課題に対する自社の姿勢や知見」を伝える場として。SNSや広告のような瞬間的な接点だけでは伝えきれない“背景”や“想い”を伝える場所として活用されます。
また、オウンドメディアはSEOとの相性も良く、ユーザーが検索してたどり着いたときに信頼感や共感を与えることで、問い合わせや採用応募といった次の行動につなげることもできます。
オウンドメディア運用でよくある悩み
更新が止まり、放置されたサイトになってしまっている
立ち上げ当初は意欲的に記事を更新していたものの、時間の経過とともに社内の確認が追いつかず、気づけば数ヶ月更新が止まっていた。こうした“放置状態”に陥ってしまうメディアは少なくありません。例えば、月2本の更新目標を立てたものの、執筆者が業務と兼務だったため継続できず、「続けられないならやめた方が良いのでは」といった声が社内で上がってしまうケースもあります。
誰に向けたメディアかが曖昧で、内容に一貫性がない
サービス紹介、採用、CSR活動、社内文化…。あらゆるトピックが混在し、メディア全体の軸が見えづらくなってしまう。たとえば、サービス紹介記事の隣に社員の休日紹介が並び、「このサイトは何のためのメディアなのか」が読者にも社内にも伝わらない状態に。ターゲットや目的を明確に定めないまま始めると、後から方向性の見直しに大きな労力がかかってしまいます。
社内確認や原稿修正に時間がかかり、運用が前に進まない
原稿はできているのに、公開までは数週間…。理由は社内フローにあります。広報・マーケだけでなく、法務や現場担当のチェックが必要な体制だと、1本の確認に複数名が関わり、進行が滞ってしまうことも。特にインタビュー記事や事例紹介では、確認すべき情報が多く、関係者とのやり取りに時間がかかる傾向があります。
費用と時間がかかりすぎて、費用対効果が合わない
毎月の更新で「記事1本に数万円、外注コストがかさんでいる」「制作に時間がかかり、他業務に支障が出る」と感じるようになると、メディア運用そのものが“贅沢なコスト”と見なされてしまいます。特にKPIが曖昧なままだと、「成果が見えないからやめよう」という判断になりやすく、運用の継続が難しくなります。
目的が“PV集め”になってしまっている
「月間〇万PVを目指そう」という目標が先行し、検索ボリュームの多いテーマばかりを追いかけてしまう。結果として、ターゲットや自社の提供価値からズレた内容が増え、「誰に何を伝えたいのか」が薄れてしまうケースもあります。特に採用やブランド目的のメディアでは、量やアクセス数よりも“読んだ人がどう感じたか”の方が重要な指標になります。
toritokeのオウンドメディア運用代行ではこのように解決します
01|戦略・制作・進行を分担できる専任体制で、無理なく継続できる運用を実現
オウンドメディア運用において最も多い課題のひとつが、「継続できない」ことです。toritokeでは、ディレクター・編集者・ライターを基本とした3名以上の専任体制を構築し、社内の工数を抑えながら、安定して“継続できる運用”を支援します。
ディレクターは全体の戦略立案とスケジュール管理、編集者は記事の質と一貫性の担保、ライターは構成案と原稿執筆を担当。それぞれの役割を明確に分担することで、業務負担を分散しつつ、記事制作の属人化を防ぎます。
たとえば、月2〜4本の記事を制作する企業に対して、「1回のネタ出し会議→構成共有→原稿確認」という流れをテンプレート化。社内での対応は週1回の確認作業に留め、無理なく継続できるワークフローを整えます。
02|限られた予算でもスタートできる、柔軟で実践的な支援プラン
「記事を作りたいが、予算の制約がある」「続けたいけど費用対効果が合わない」そうした声に応え、toritokeでは月額10万円から始められるマーケティング支援プラン「WebStrat」をご用意しています。
このプランでは、記事制作に加えて、CTAボタン設計、導線調整、アイキャッチ画像の作成、タグ設計といった“見た目と成果をつなぐ支援”まで一貫して対応が可能になります。記事の数や更新頻度だけでなく、「どこを改善すれば成果が出るか」を考えた構成で進行します。
例えば「記事制作1本+構成案作成+ホワイトペーパー設計」や、「記事2本+Instagramリール動画3本」のような形で、事業課題やターゲットに応じて柔軟に組み合わせが可能です。限られたリソースの中でも、無理なく始められる範囲を一緒に設計し、成果につなげるための支援を行います。
03|“成果につなげる運用”を実現する、KPI設計と分析・改善の仕組み
オウンドメディアを継続的に成果へつなげるには、あらかじめ目指す成果に対して「何を指標にするか」を明確にし、その後の運用に組み込んでいく仕組み化が欠かせません。
まず、目的ごとに適したKPIを設計します。
- リード獲得を目的とする場合:「資料DL数」「お問い合わせ遷移数」「CTAクリック率」
- 採用広報を目的とする場合:「採用ページへの遷移数」「エントリーフォーム到達率」「記事ごとの平均滞在時間」
といったように、単なるPVではなく成果に結びつく動きに着目した指標を設けます。
また、目標設定だけでなく、毎月の振り返り→改善までをひとつの流れとして運用支援。Googleアナリティクス4での行動データ、ヒートマップでの視覚分析、検索クエリや掲載順位の推移といった複数の視点から「どのコンテンツが効果を生んでいるか/どこに課題があるか」を定点観測します。
オウンドメディア運用代行サービス概要
ペルソナ/カスタマージャーニーマップによるターゲット整理
成果につながるオウンドメディア運用には、まず「誰に読まれるべきか」を明確にする設計が欠かせません。想定読者の属性や課題、行動パターンを言語化し、カスタマージャーニーに沿って必要な情報を整理します。たとえば、地域密着型の住宅会社であれば「初めての家づくりで何を基準に選べばよいか分からない」30代夫婦をペルソナとし、悩み→比較→相談へ進む導線を設計します。
キーワード調査およびテーマ設計
検索流入やSNSでの拡散、記事同士の連携によるサイト全体の評価向上を実現するには、緻密なキーワード戦略とテーマ設計が欠かせません。Googleサジェスト、キーワードプランナー、競合分析などを通じて、ユーザーの検索意図や課題を可視化し、情報設計に落とし込みます。
たとえば、BtoBの業務管理クラウドを提供する企業では、「業務効率化 ツール 比較」「クラウド 勤怠管理 導入メリット」「中小企業 DX 事例」など、ニーズが明確なキーワードを軸に、トップページ・サービスページと連動した記事を設計します。
さらに、SEOの文脈では**トピッククラスター(主軸となるテーマとその周辺トピックの連携構造)**を構築することで、検索エンジンからの専門性評価を高めると同時に、ユーザーの回遊導線も整える設計が可能です。
一方、BtoCの脱毛サロンなどの場合には、「メンズ 脱毛 東京 おすすめ」「脱毛 何回目で効果」「VIO 脱毛 初心者」など、悩み・目的・地域性に応じたキーワードを起点に、集客や予約につながるテーマを策定します。
また、インタビュー記事や広報的なブランディング記事については、キーワードよりも「誰の声をどう届けるか」「何を言語化すべきか」といった観点から、記事テーマや切り口の棚卸し・整理を実施。代表メッセージ、社員インタビュー、SDGsや社会貢献の取り組みなど、ブランドの世界観を伝える企画テーマを洗い出していきます。
コンテンツガイドラインの策定
メディアの品質を安定させ、複数人での制作体制でもスムーズに進行できるように、表現ルールを明文化したコンテンツガイドラインを策定します。例えば「文体はです・ます調に統一する」「見出しごとの段落数は最大3つまでにとどめる」「数字は半角表記とする」「1文は180〜200字を目安とする」といったルールを定めることで、執筆やレビューの効率が向上します。
また、表記揺れや読みづらさを防ぐために、漢字のひらき方や送り仮名の方針もあらかじめ定めておきます。たとえば「子供」か「子ども」、「出来る」か「できる」など、企業や読者層に合わせた語彙ルールを決めることで、文章の一貫性と読みやすさを高めます。
このようなガイドラインを整備することで、制作物全体に統一感が生まれ、担当者が変わっても品質を維持しやすくなります。媒体としての信頼性や継続的な運用体制づくりにも貢献する、大切な設計工程のひとつです。
コンテンツ計画の立案
記事や投稿は、思いつきで更新していては「情報の偏り」や「更新停止」に陥りやすくなります。そこで、事業スケジュールや社内イベント、季節性、ユーザーの検討フェーズなどを踏まえた中長期のコンテンツカレンダーを作成します。
たとえば、BtoBの製造業では、展示会前に「出展製品の解説記事」、年末には「今年の業界トレンドまとめ」、新年度には「中途採用強化に関するコンテンツ」など、事業活動に合わせたタイミングで記事や動画を配置します。BtoC企業であれば、夏前に「UV対策の解説記事」、年末に「プレゼント需要を意識した特集ページ」を制作するなど、季節性も重要です。
さらに、イベントやキャンペーンに連動した記事(例:「◯月のセールと連動した新商品紹介」)などもあらかじめ設計。先を見越した準備ができることで、社内の確認工数も分散され、安定的な更新サイクルが実現できます。
オウンドメディアのKPI設定
「PVが増えたかどうか」だけでは、オウンドメディアの成果は測れません。重要なのは、“何を目的にメディアを運用しているのか”に応じて、適切な評価指標(KPI)を設定し、その数字をもとに改善と判断ができる状態をつくることです。
例えば、リード獲得が目的であれば、「資料ダウンロード数」「お問い合わせフォームへの遷移数」「CTAボタン・バナーのクリック数」などが主な評価指標になります。また、同一ユーザーによる複数回の訪問(リピート訪問数)を追うことで、関心度の高いコンテンツや見込み顧客の動きも把握しやすくなります。
採用広報が目的の場合は、「採用ページへの遷移」「平均滞在時間」「エントリーフォームの閲覧数・完了率」などが指標として有効です。加えて、Google検索やSNS、メールマガジンなど、流入チャネルごとのパフォーマンスを分析することで、どの媒体からの流入が最も成果につながっているのかを明確にできます。
このように、メディアの目的に応じて評価軸を定め、成果を定点観測できる状態をつくることで、「何を改善すべきか」「次にやるべきことは何か」が見えやすくなります。闇雲な発信や曖昧な運用から脱却し、事業成長に貢献するメディアとして活かしていくための土台を整えます。
継続できる運用体制の構築
どれだけ良い記事を作っても、更新が止まればメディアの価値は急落してしまいます。継続的な発信を実現するためには、社内体制の整備と運用の仕組み化がカギです。
たとえば、担当者が1人だけで進める場合は、「月1回30分のネタ出し会議」「確認はチャットで簡易チェック」「構成や文章は外注活用」など、最小限の稼働で回る設計にします。また、複数部署が関わる場合は、タスク分担と確認フローを明確にし、役割が属人化しないようテンプレートや進行管理表を整備します。
タスク管理は「何を」「いつまでに」「誰がやるか」が一目でわかるよう、Googleスプレッドシートを活用して管理します。運用が人の頑張り頼りにならない体制を整えることで、継続の難易度は大きく下がります。
数値レポーティングによる改善提案
オウンドメディアの運用において重要なのは、「公開して終わり」ではなく、数値に基づいた改善を継続することです。私たちは、アクセス解析・検索データ・ユーザー行動ログなどを総合的に分析し、改善の方向性を明確にします。
Googleアナリティクス4を活用し、記事別のセッション数・ユーザー数・平均滞在時間・離脱率を定点観測。さらにヒートマップツールを用いて、「どこまで読まれているか」「どの要素がクリックされていないか」といったユーザーの動きを視覚的に把握します。
Googleサーチコンソールでは、検索クエリの表示回数・クリック数・CTR・平均掲載順位を分析。GRCなどの順位チェックツールも併用し、狙ったキーワードの検索順位の推移を継続的に追跡します。
たとえば、「記事のセッションは多いが、CTAまで読まれていない」といった場合は、CTAの位置や文言、導入部分の構成に改善余地があるサインです。また、「検索流入があるのに滞在時間が短い」場合は、タイトルやファーストビューの見直しが必要かもしれません。
これらの分析結果は月次レポートとしてご提出し、改善点と施策案もセットでご提案します。次に何をすべきかが明確になり、運用が“回るだけ”で終わらず、成果に直結する改善が可能になります。
オウンドメディア運用に関する記事
オウンドメディアとは?AI時代の運用やメリット、成功事例まで解説
オウンドメディア立ち上げ完全ロードマップ!戦略からKPI、費用相場まで総まとめ
【保存版】オウンドメディアにかかる費用を総まとめ!年間コストと内訳のシミュレーション付
オウンドメディアのKPI設計を戦略的に!CVから商談化・契約までつなげるファネルと主要KPI
オウンドメディアは運用が9割!成果に導く3つの体制と改善プロセス
オウンドメディア運用のご相談を無料受付中!
私たちは、オウンドメディアを「企業やサービスの“想い”を伝え、信頼と共感を育む場」だと考えています。
ただ記事を増やすのではなく、「誰に」「何を」「どの順番で」伝えるべきかを設計し、メディア全体として目的を果たすための運用支援を行っています。
「更新が止まってしまった」「内容に一貫性がなく伝わらない」「効果が見えず続けられない」──
そんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。現在のメディア構成や記事内容、運用体制の状況をもとに、目的達成に向けた改善方針をご提案します。
無料相談申し込みフォーム
「リソースが限られていて迷っている」「社内だけでは続けられるか不安」といった段階からでも構いません。無料相談では、ターゲット設計、コンテンツ方針、更新体制、数値管理などについて、貴社の現状を踏まえながらご相談に応じ、最適な方向性をご提案します。