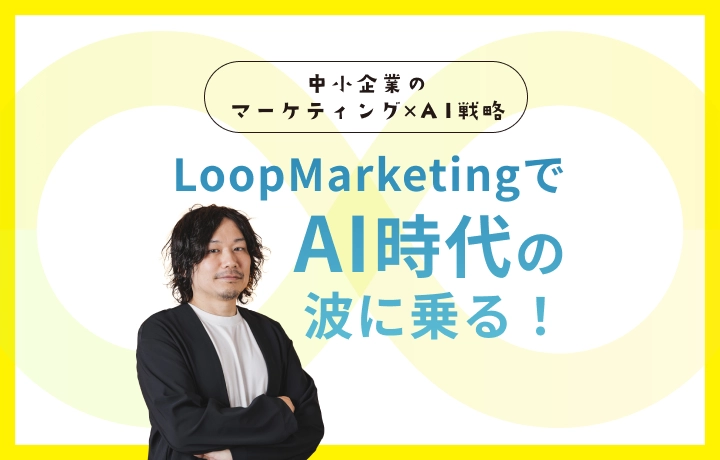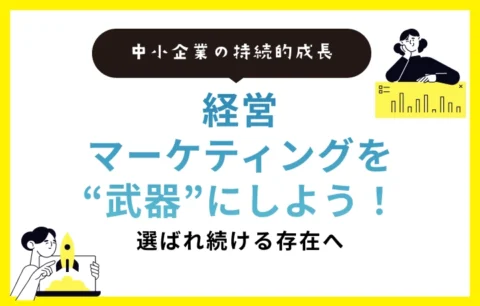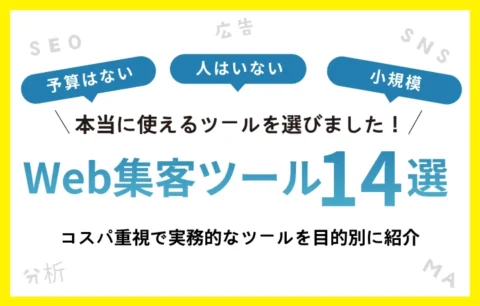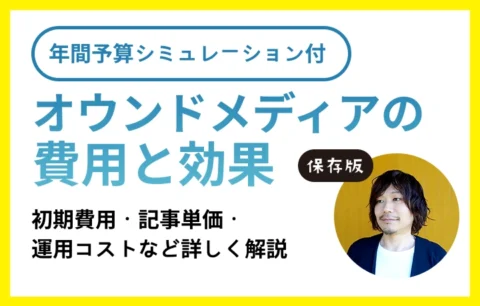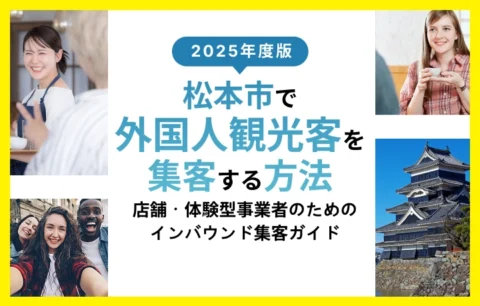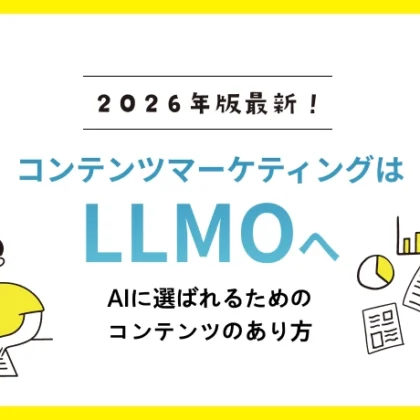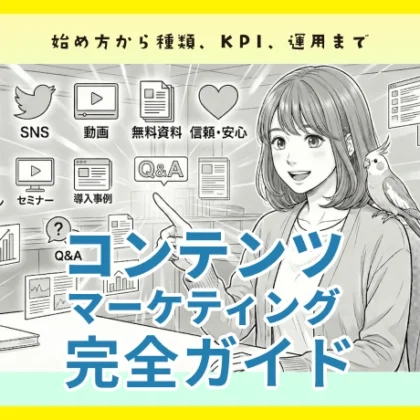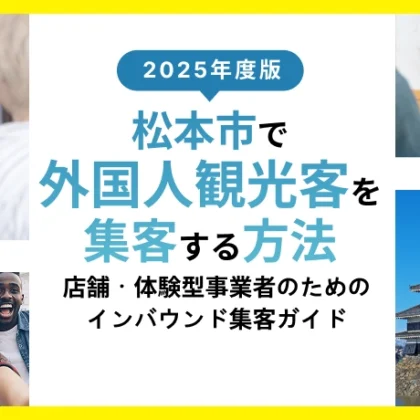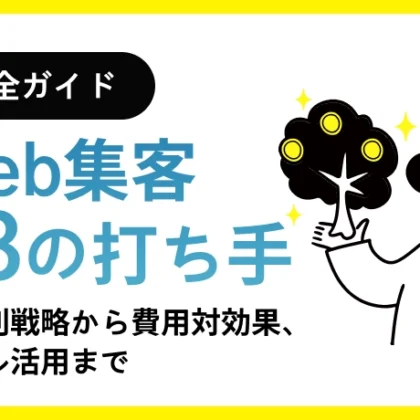従来のマーケティングは「ファネル型(認知→検討→購入)」が主流でしたが、生成AIやAI検索の普及により、ユーザー行動や情報接触のプロセスは大きく変化しています。こうした時代に注目されているのが、「LoopMarketing(ループマーケティング)」という考え方です。
LoopMarketingは、顧客との接点や体験の質を高めながら、AIとの連携を前提に“循環するマーケティング”を設計していく手法です。顧客行動の蓄積や生成AIによる出力内容までも意識し、全体を戦略的に最適化していきます。
本記事では、中小企業でも実践できるLoopMarketingの構成要素と、ファネルやフライホイールとの違い、そしてAI時代に必要なKPI設計・顧客体験設計のポイントを具体的に解説します。
▼この記事の監修者
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

この記事の内容は、株式会社toritokeの「経営マーケティングラジオ」でもお聴きできます。中小企業や個人事業主に向けて経営やマーケティング課題を解決することをテーマにしています。定期的に配信しておりますので、フォローいただけると嬉しいです。
LoopMarketing(ループマーケティング)とは

LoopMarketingとは、HubSpot社が2025年に提唱した、新しい成長戦略のフレームワークです。従来のファネル型モデルや、同社が提唱してきたフライホイールモデルをベースにしながら、AI時代の購買行動や顧客接点の多様化に対応するために進化したマーケティング思想として注目を集めています。
「The Loop」とも呼ばれるこのモデルは、単なる施策の連続ではなく、「ブランドの表現(Express)→ パーソナライズ(Tailor)→ 拡散(Amplify)→ 改善(Evolve)」という4つのサイクルを繰り返すことで、顧客との関係性を深めながら、AIと人間の強みを掛け合わせて成果を高めることを目指します。
HubSpot自身が、「AI効率(Efficiency)」と「人間らしさ(Authenticity)」の両立を掲げており、AIによる最適化と、人の共感や判断を組み合わせた“循環型マーケティング”の実践モデルだと言えるでしょう。
参考:Loop Marketing | AI時代の成長を実現するHubSpotの新しいプレイブック|HubSpot(ハブスポット)
LoopMarketingが注目される理由
マーケティングを取り巻く環境は、ここ数年で劇的に変化しました。
- 生活者は検索だけでなく、SNS・口コミ・生成AIなど、複数のチャネルを行き来しながら意思決定を行うようになった
- AIの進化によって、マーケティング業務の自動化やパーソナライズが進んだ
- 情報が溢れる時代だからこそ「人間らしさ」や「共感」がより一層求めらている
このような状況では、従来の直線的なファネルモデルでは、生活者の複雑な動きを捉えきれなくなってきたという課題があります。
LoopMarketingは、以下の理由から、いま再注目されているアプローチです。
1. 生活者の行動は「ループ」している
検索 → 比較 → 購入 → 使用 → 発信(口コミ)→ 再購入。
このように、生活者の行動は一方通行ではなく、体験と情報の循環の中で進化していきます。LoopMarketingはその循環構造を前提に、施策やコミュニケーションのあり方も“循環型”として設計します。
2. AIと人の役割を共創するフレームワーク
AIにより、データ解析・自動化・パーソナライズは可能になりますが「選ばれる」には生活者との信頼関係や、本物らしさ(Authenticity)が欠かせません。
LoopMarketingは、HubSpotが提唱する「Efficiency × Authenticity」の実現を支える構造であり、AIと人の役割分担を前提とした協働型マーケティングです。
3. 全社で「関係性を育てる」視点が必要に
LoopMarketingでは、マーケティング・セールス・カスタマーサクセスといった部門を越えた関係性構築の循環を設計することが前提となります。特定の施策ではなく、企業全体でブランド体験を届ける仕組みづくりが求められます。
4. 中小企業にも実装しやすい現実的な循環型マーケ
LoopMarketingは、必ずしも高機能なツールや巨大なリソースを前提としていません。
本質的な価値提供の流れを、繰り返し改善しながら構築していくという発想は、むしろ小さな組織だからこそ機能します。
本質的な価値提供の流れを、繰り返し改善しながら構築していくという発想は、むしろ小さな組織だからこそ機能します。大きな企業のように複雑な階層や意思決定プロセスがないぶん、試行錯誤をすぐに反映できる柔軟性があるのです。
私自身、日々中小企業の経営者や現場の方々と向き合いながら「伝え方」「届け方」「受け取られ方」のズレが、機会損失や誤解を生んでしまう経験をしました。「LoopMarketing」という考え方は、単なるフレームワーク以上の可能性を感じています。
- 商品やサービスの良さを、正しく届ける循環をつくる。
- 一度の発信で終わらせず、接点を重ねながら“信頼”を育てる。
このループを、企業の規模にかかわらず設計・運用していくことこそが、マーケティングの本質であり中小企業の強みを最大限に活かす方法なのではないかと思うのです。
従来のファネル型との違いとフライホイールモデルとの関係
LoopMarketingの特徴を理解するうえで欠かせないのが、従来のマーケティングモデル。特に「ファネル型」との違いです。
従来のファネルモデルが抱える限界
ファネル型マーケティングは、認知から購入までを一方向で捉えるモデルであり、構造としてはシンプルで扱いやすい点が特長です。しかし、購入後の体験や、顧客との長期的な関係構築といった視点は反映しにくく、再購入や紹介といった循環の設計が抜け落ちてしまうケースも少なくありません。
また、ファネルは「入口を広くすれば、ある一定割合が自然とゴールに至る」という確率論に基づく考え方です。しかし、現代の生活者やBtoB企業の購買行動は、必ずしも一直線ではなくなっています。
例えばSNSや口コミ、比較サイト、レビュー動画、リアルな体験イベントなど、多様な情報源を行き来しながら立ち止まり、迷い、時には離脱し、また戻ってくるといった複雑なプロセスが当たり前になっています。
このような購買行動の変化においては、「上の母数を増やすほど成果が出る」といった旧来的なロジックは通用しづらくなっています。むしろ、接点のひとつひとつでどれだけ信頼を築けるか、そしてその体験がどう循環していくかが問われる時代です。
LoopMarketingでは、こうした顧客の行動様式を前提に、マーケティングの各接点をつなげながら、全体で価値が循環する仕組みをつくることを重視しています。
フライホイールモデルの違い
LoopMarketingは、同じくHubSpotがかつて打ち出したフライホイールモデルをベースにした考え方です。両者とも「顧客との関係性が継続し、成長が循環していく」という点では共通していますが、その設計思想と適用領域には明確な違いがあります。
共通点:どちらも「循環」を重視している
LoopMarketingは、HubSpotがかつて提唱したフライホイールモデルをベースにした概念です。両者に共通するのは、「顧客との関係性を一度きりで終わらせず、継続的に循環させていくこと」に重きを置いている点です。
いずれのモデルも「売って終わり」ではなく、顧客との関係を持続させて次の接点に活かしていくという発想です。
違い①:LoopMarketingは“現場で回せる実践モデル”
フライホイールモデルは、思考の転換として優れていますが、現場にとっては「どこから始めるか分からない」「摩擦(friction)をどう捉えるか分かりにくい」といった課題がつきまとうこともあります。
LoopMarketingはこうした抽象性を補う形で、以下の4ステップで改善を回す実践フレームとして設計されています。
- EXPRESS(表現する) ブランドの価値や想いを、テキスト・ビジュアル・ストーリーで具体化
- TAILOR(個別化する) ターゲットやチャネルに合わせて情報を最適化
- AMPLIFY(増幅する) 複数チャネルで展開し、広がりを生む仕掛けを作る
- EVOLVE(進化する) データをもとに反応を分析し、改善・進化させる
このようにLoopMarketingは、「施策をどう繋ぎ、どう回すか」までを現場視点でガイドする設計となっており、少人数のチームや専門部署がない企業でも取り組みやすいのが大きな特徴です。
違い②:LoopMarketingはAI活用を前提としている
LoopMarketingの大きな特徴の一つは、AIの活用をマーケティングの中核に据えていることです。
フライホイールモデルが「人を中心に据えた関係性マーケティング」として設計されていたのに対しLoopMarketingは、生成AIなどのテクノロジーと人の力を組み合わせて、マーケティングを共創するモデルへと進化しています。少人数チームや中小企業でも、限られたリソースで効果的に取り組めるのはこの柔軟性ゆえです。
LoopMarketingにおけるAIの役割例
- EXPRESS(表現):ブランドの価値や想いを、生成AIでテキスト・ビジュアル・ストーリーとして具体化
- TAILOR(個別化):顧客やチャネルごとに、メールや広告、LPなどの内容をAIが最適化
- AMPLIFY(増幅):複数チャネルへの自動投稿や、AIによるA/Bテストでの反応最適化
- EVOLVE(進化):顧客の反応データをもとに、改善点を抽出し、再展開・最適化を自動化
こうしたAIとの役割分担により、LoopMarketingは「実行のハードル」と「改善のスピード」の両立が可能となっています。
人のクリエイティビティと、AIによるオペレーション最適化が循環することで、再現性の高いマーケティングサイクルを構築できる。これこそが、LoopMarketingの中核的価値です。

私自身、複数の中小企業様の現場を支援していて実感するのは、ファネルでは説明しきれない行きつ戻りつする顧客行動です。LoopMarketingは、そのリアルな動きを前提に設計できる点で、非常に実務に即していると感じています。

フライホイールモデルで小さな会社の成長戦略を描く!実践方法と仕組み作り
LoopMarketingの4つの要素
LoopMarketingは、マーケティング活動を以下の4つのフェーズ(EXPRESS → TAILOR → AMPLIFY → EVOLVE)に分け、それを循環させながら改善していくモデルです。従来のように施策ごとに断絶された流れではなく、全体がつながった仕組みとして機能するのが最大の特徴です。
ここでは、それぞれのステップを具体的な事例とともに紹介します。
1. EXPRESS(表現する)
このフェーズは、LoopMarketingのすべての循環をスタートさせる“出発点”であり、ブランディングの中核を担う最も重要なフェーズです。
企業やブランドが「どんな存在で、誰に、どんな価値を提供するのか」。この存在意義と伝えるべき価値を、言葉とビジュアルの両面で定義し、統一されたメッセージに落とし込むことが目的です。
ここが曖昧なままだと、以下のような問題が現場で発生します。
- 発信内容がチャネルごとにバラバラになる
- 社内メンバー間でも「何を伝えたいのか」が共有されていない
- 顧客にとって「このブランドは何者なのか」が伝わらない
こうした情報の断片化は、マーケティング全体の成果を著しく下げる要因となります。LoopMarketingではこのEXPRESSフェーズを全体設計の土台として最重視しています。
EXPRESSフェーズにおける実務とAI活用の例
このフェーズでは、単なるアイデア出しにとどまらず、メッセージの“具体化と検証”を高速で繰り返すことがカギになります。
現場での実践例
- ブランドコピーの複数案をAIと共に生成 → チームで比較・評価・決定
- 理念や創業ストーリーをもとにナラティブを構成
- ペルソナごとの“刺さる言葉”をパターン化し、訴求メッセージを整備
このように、価値の言語化とビジュアル化を並行して行い、社内外で共有可能な伝わる設計に落とし込むことが、このフェーズのゴールです。
2.TAILOR(個別化する)
このフェーズでは、届けたい相手に合わせてメッセージや表現方法を最適化することが求められます。LoopMarketingにおいてTAILORは、表現したブランドメッセージを「誰に」「どのチャネルで」「どのように届けるか」という実務的な設計フェーズです。
EXPRESSフェーズで定義された“伝えるべき価値”が、すべての顧客に同じように響くとは限りません。ペルソナやセグメントごとのニーズ・リテラシー・関心に応じて、適切な言葉・表現・タイミングを選び直す必要があります。
この設計が不十分だと、以下のような問題が発生します。
- 伝えたいことが正しく届かない(読まれない・見られない)
- 情報量が過不足となり、かえって離脱につながる
- 「自分向けではない」と判断され、選ばれにくくなる
顧客の数だけ情報の届き方が異なる時代において、この個別最適化は欠かせない工程となっています。
TAILORフェーズにおける実務とAI活用の例
このフェーズでは、セグメントごとに適したメッセージングやチャネル戦略を素早く検討・実行するため、生成AIの「情報分解力」と「文章調整力」が大きな力を発揮します。
現場での実践例
- ペルソナ別に訴求ポイントを再整理し、メール・LP・動画などのコンテンツを最適化
- 顧客セグメントごとにトーンや語彙を調整したコピーを生成・比較
- 複数チャネル(LINE、Instagram、X、メール等)に合わせた表現分岐の案出し
- デバイス(スマホ/PC)や利用タイミング(通勤中/就業中)に合わせた構成案の検討
例えば、「ITに不慣れな経営者層」向けには専門用語を排除し、わかりやすい言葉で安心感を強調。一方で「現場の担当者」向けには具体的な操作性や活用シーンを中心に構成するなど、届ける相手に合わせたチューニングが求められます。
3.AMPLIFY(増幅する)
このフェーズは、表現(EXPRESS)し、個別化(TAILOR)したメッセージを「広がりのある接点」に展開していく段階です。単なる拡散ではなく意味のある接触を増やすことが目的です。
生活者は日常的に複数のチャネルを行き来しているため、どこで接触しても一貫したブランド体験を感じられるように設計することが重要です。ここが弱いと、せっかく整えたメッセージも断片的に届き、ブランド体験として積み上がりません。
ここが曖昧なままだと、以下のような問題が発生します。
- 拡散の仕方が場当たり的になり、せっかく整えたメッセージが断片的に届いてしまう
- 投稿や広告が「一度きりの接触」で終わり、関係性の深まりにつながらない
- 複数チャネルで同じ情報を流すだけになり、「ノイズ」として受け取られてしまう
- 拡散後の反応が収集されず、次の施策に活かされない
AMPLIFYは単純な露出の増加だけではなく「生活者が意味を感じる接触をどれだけ積み重ねられるか」を設計するフェーズです。ここを整えることで、ブランド体験が断片ではなく循環として積み上がっていきます。
AMPLIFYフェーズにおける実務とAI活用の例
このフェーズでは、コンテンツを複数のチャネルに展開しながら、AIによる自動最適化と反応分析を取り入れることで、少人数でも効率的に広がりを生み出せます。
- 1つのコンテンツを基に、Instagramリール・X投稿・YouTubeショート・ブログ記事・メール配信などへ再編集
- チャネルごとに反応が高い表現をAIが分析し、配信パターンを調整
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)を促す質問・アンケート・投票を組み込み、SNSでの二次拡散を誘発
- 広告や投稿のクリエイティブをAIが自動生成・テストし、成果の良いものを優先配信
例えば、ある小売店が新商品の告知を行う場合、AIは「リピーター顧客」には特典情報を強調したメールを送信し、「新規フォロワー」には商品の魅力を伝えるSNS広告を配信するといった形で接触内容を調整できます。さらに、LINEでは購入後のフォローアップを行うことで、複数チャネルをまたいだ一貫した体験を提供できます。
4.EVOLVE(進化する)
このフェーズは、これまで展開した施策や接触から得られた反応を分析し、改善や進化につなげる段階です。データを集めるだけではなく「次の循環にどう活かすか」を設計することが目的です。LoopMarketingにおけるEVOLVEは、施策の検証・改善を繰り返し、全体のループを強化していく役割を担います。
ここが曖昧なままだと、以下のような問題が発生します。
- データが蓄積されても、改善につながらず“やりっぱなし”になる
- 成果が属人的な判断に左右され、再現性が生まれない
- 顧客の声や反応が施策に反映されず、同じ失敗を繰り返す
- PDCAではなく「P止まり」で、ブランド体験が成熟しない
EVOLVEは、収集したデータやフィードバックを循環の燃料に変えるフェーズです。ここを整えることで、マーケティング全体が継続的に進化し、顧客との関係性が深まっていきます。
EVOLVEフェーズにおける実務とAI活用の例
顧客の反応や行動データを分析し、改善点を抽出・再展開することが重要です。生成AIを活用することで、大量のデータを短時間で要約し、具体的な改善アクションに落とし込むことが可能になります。
- SNSやメールの反応率を分析し、効果の高いメッセージや時間帯を抽出
- 顧客アンケートやレビューをAIで要約し、改善ポイントを明確化
- LPや広告のクリックデータを解析し、訴求要素を入れ替えた新しいパターンを生成
- 顧客セグメントごとの行動データを基に、リピート施策やクロスセル施策を設計
例えば、BtoBのITサービス企業がホワイトペーパーのダウンロード施策を行った場合、AIは「フォーム入力時の職種データ」や「その後のメール開封・クリック状況」を分析し、次回は経営層向けにはROIの訴求を強化し、現場担当者向けには具体的な導入手順や成功事例を追加する、といった改善策を提示できます。
こうして分析と改善を積み重ねることで、施策は次の循環でさらに精緻化され、リード獲得から商談化への転換率を高めていくことができます。

今の時代、AIは単なる効率化の道具ではなく、「表現→個別化→増幅→進化」のあらゆる段階で役割を果たします。AIを使えば試行回数を一気に増やせるので、改善のサイクルを回すスピードが格段に上がります。ただし重要なのは、AIに任せきりにせず、人が方向性や価値観を決めて、AIをその循環の中で動かす設計をすることです。
LoopMarketingでKPIはどうなる?
LoopMarketingでは、従来のファネル型でよく見られる「直線的な数値管理」とは異なるKPI設計が求められます。ファネルでは「セッション数 → フォーム遷移率 → 完了率 → 商談率 → 成約率」といった一方向の指標設計が中心でした。しかし、顧客行動が複雑化・循環化している現在、この直線的なKPIだけでは実態を捉えきれません。
ファネル的KPIの限界
- 各ステップが分断され、途中で離脱した顧客が再び戻る動きを把握できない
- 「流入数を増やせば成果も比例して増える」という前提が崩れている
- 購入後の体験や紹介(リファラル)が成果指標に含まれにくい
ループ設計におけるKPIの考え方
LoopMarketingでは、「点」ではなく「流れ全体」を測る発想が必要になります。
- 接触の循環度 顧客がどの程度繰り返しブランドと接触しているか(リピート率、再訪率、メルマガ開封継続率など)
- 体験の共有度 顧客が自発的にブランド体験を広げているか(SNSでの言及数、口コミ、紹介経由のリード数など)
- 改善の速度 施策を出してから反応を検証し、改善を実装するまでのサイクルの速さ
- 関係性の深まり 顧客がどの段階で「購入者」から「ファン」へ移行しているか(アップセル率、NPS、継続率など)
LoopMarketingにおけるKPI例
| フェーズ | 観点 | 主なKPI例 | 補足(ファネルからの読み替え) |
| EXPRESS(表現する) | ブランド価値の浸透度 | ・ブランド想起率 ・指名検索数 ・Webサイト直帰率の改善 ・セッション数(新規/リピート比率) | ファネルでは「セッション数=流入母数」だったが、Loopでは “訪問者がブランドを理解し、再訪するか” に注目 |
| TAILOR(個別化する) | 適切さ・共感度 | ・メール開封率 ・クリック率 ・セグメント別反応率 ・資料DL後の継続接触率 | ファネルでは「資料DL=CV」として終点扱いだったが、Loopでは DL後に継続的な接触や行動が生まれているか を評価 |
| AMPLIFY(増幅する) | 広がりと接触の循環 | ・再訪率 ・SNSエンゲージメント(いいね・シェア) ・UGC件数 ・広告の二次効果(指名検索増加・アシストCV) ・問い合わせ数の再接触率 | ファネルでは「問い合わせ件数」がゴールだったが、Loopでは 問い合わせが単発で終わらず、再接触・紹介・拡散につながっているか を測る |
| EVOLVE(進化する) | 改善と循環の強化 | ・改善サイクル速度(施策→改善までの日数) ・NPS/満足度 ・リピート率 ・紹介経由リード数 ・商談化率 | ファネルでは「成約率」が最終KPIだったが、Loopでは 成約を起点にリピート・紹介を生み、次のループを育てているか を評価 |
KPIのポイント
- セッション数 → 数ではなく「新規/再訪」「指名検索」「直帰率」で評価
- 資料DL数 → 件数ではなく「DL後の継続接触率」で評価
- 問い合わせ数 → 件数ではなく「問い合わせ後の再接触率」や「紹介につながったか」で評価
- 成約率 → ゴールではなく「リピート率」「紹介経由リード数」につながっているかで評価
KPIの見方:よい例/悪い例
セッション数(流入)
- × 悪い例:「今月のセッション数が2倍になった!だから成果も増えるはず」
- ○ 良い例:「新規流入は多いが、再訪率が低い。表現の段階でメッセージが伝わっていないのでは?」
数字の多さではなく、再訪や指名検索につながっているかで評価します。
資料ダウンロード(リード獲得)
- × 悪い例:「ホワイトペーパーのダウンロードが100件あった!=成果」
- ○ 良い例:「ダウンロード後にメールを開封したのは30%。さらにLINEでつながったのは15%。個別化の設計を見直そう」
ダウンロード数は入口にすぎない。LoopMarketingでは「その後の接触の継続率」で評価します。
問い合わせ数
- × 悪い例:「問い合わせが20件あった!これでゴール達成」
- ○ 良い例:「問い合わせ20件のうち、再度サイトに訪問したのは8件、SNSフォローに至ったのは5件。増幅の段階で循環が起きている」
単発の問い合わせ件数ではなく、その後の再接触や紹介につながっているかを重視します。
成約率
- × 悪い例:「成約率が20%。ここで終わり」
- ○ 良い例:「成約顧客のうち、30%がリピート購入、10%が紹介経由で新しいリードを生んだ。進化の段階が機能している」
成約はゴールではなく、リピートや紹介を生む起点として評価します。

ページビューやダウンロード件数といった「点」のKPIは、もはや成果を語る指標にはなりません。AI時代では、顧客との接点が複雑に行き来するのが前提であり、見るべきは「流れ」や「循環の度合い」です。数字を大きくすることよりも、接触がどう循環してブランド体験を積み上げているかを測ることこそ、デジタルマーケティングの本質だと考えています。
LoopMarketingを自社で始めるために
LoopMarketingは「AIによる効率」と「人が生む信頼」を掛け合わせ、顧客との接点を循環させる考え方です。ファネルのように一度きりで終わるのではなく、接触を重ねるたびにブランド体験が積み上がっていくのが特徴です。
中小企業にとって重要なのは、いきなりすべてを整えようとしないことです。最初の一歩は、「表現(EXPRESS)」で自社の存在意義や価値を一文で言える形に整理すること。ここが曖昧なままでは、個別化や拡散、改善のサイクルも効果を発揮しません。
次に、メール・SNS・LINE・営業資料といった既存チャネルを使いながら、「誰に」「どう伝えるのが最適か」を一つずつ検証してみましょう。AIを活用すれば、文面の調整や配信の自動化などはすぐに試せます。
大切なのは、小さなループを素早く回すこと。1回の発信やキャンペーンの結果をそのままにせず、反応を拾って次の改善に反映する。この積み重ねが、やがて持続的な信頼と売上につながります。
LoopMarketingは、限られたリソースだからこそ循環を意識した取り組みが成果を大きく変えていきます。そして、自社の価値をきちんと伝え、顧客と関係を深めていく姿勢そのものが、次の時代に選ばれる企業の条件となるでしょう。
LoopMarketingを実践するにはhubspotの活用がおすすめ
HubSpotはLoopMarketingを提唱した企業でもあることから、実践する上で有用なツールです。
HubSpotを活用することで、顧客のニーズを把握し、そのニーズに合わせたマーケティング、営業、カスタマーサポートの改善が可能になります。また、膨大なデータを分析し、適切なタイミングで顧客とのコミュニケーションを行うこともできます。
導入コストも小さな会社から大企業まで幅広いプランが用意されているため、会社規模に合わせて選択できます。
弊社ではHubSpotの導入・運用支援を行っていますので、LoopMarketingを実践したい方や課題を感じている方は、ぜひご相談ください。
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー