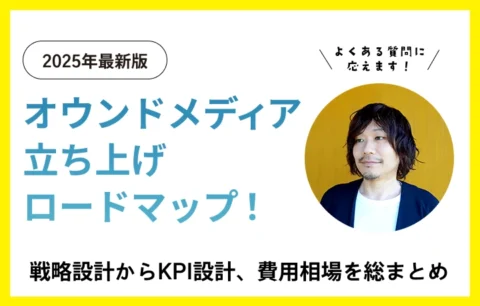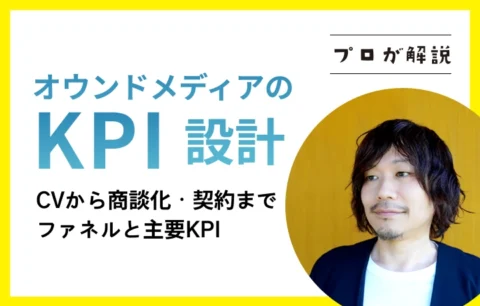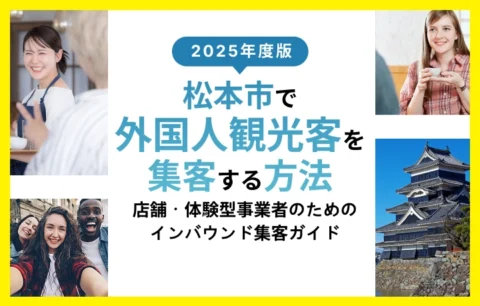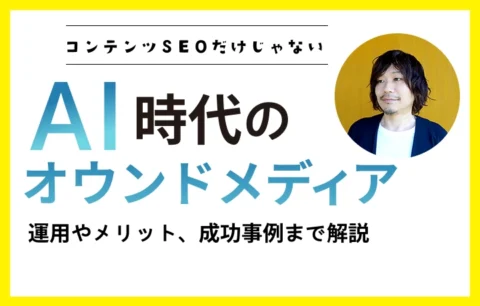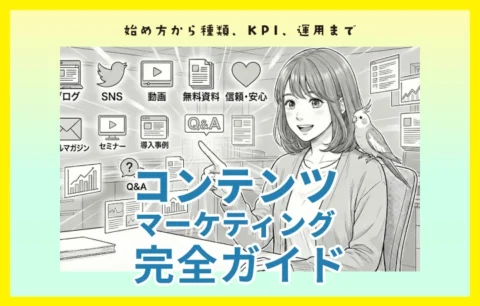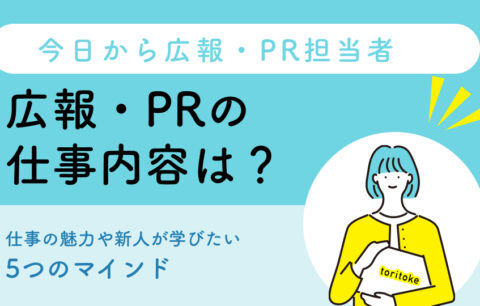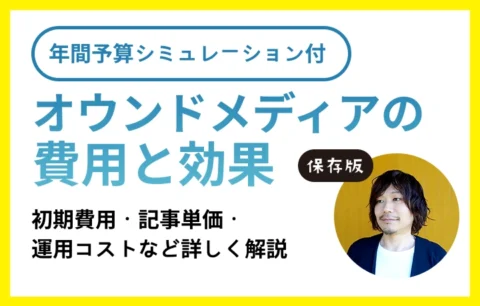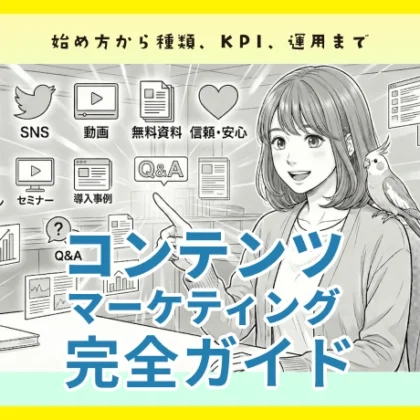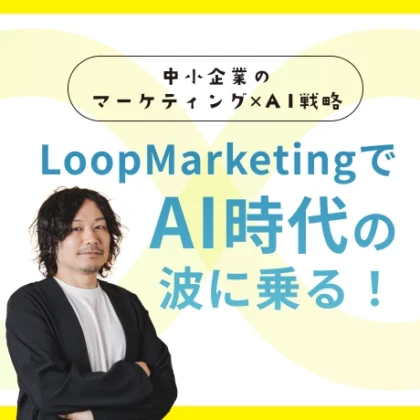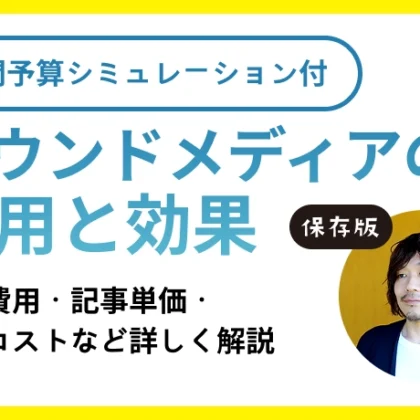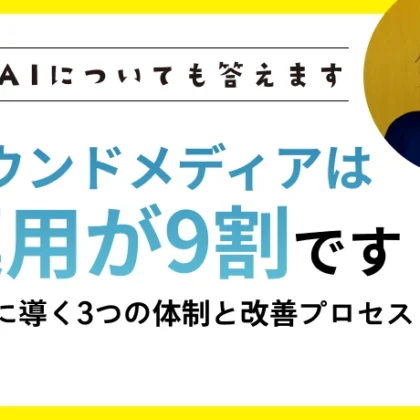「新規のお客さんがなかなか増えない」「リピーターをどう増やせばいいかわからない」——飲食店を経営していると、集客に関する悩みはつきものです。特に競争の激しい飲食業界では、チラシやSNS、Googleマップなどをうまく活用し、店舗の魅力をどう伝えるかが集客のカギを握ります。
本記事では、飲食店を運営する方に向けて、実践しやすく効果の出やすい集客テクニックを5つご紹介します。あわせて、SNSやGoogleなどを活用した即効性のあるアイデアや、地道なファンづくりにつながる工夫もお伝えします。
▼この記事の監修者
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

飲食店の集客が重要な理由とは?
飲食店にとって、集客は経営を支える重要な要素です。しかし、近年の飲食業界を取り巻く環境は大きく変化しており、単純に「美味しい料理を出せばお客さんが来る」という時代ではなくなっています。特に注目すべきは、以下の3つの要因です。
飲食業界の動向激化
新規参入が増える一方で、倒産件数も多い飲食業界は、まさに激動の時代を迎えています。関東経済産業局の「令和5年度市場競争環境評価調査」によれば、飲食サービス業は地域経済や雇用を支える重要な存在である一方、低生産性や人材不足が課題とされています。
また、上図の東京商工リサーチのデータでは、2023年の飲食業倒産件数が前年比20%増となり、特に小規模店舗での経営の厳しさが浮き彫りになっています。このような環境下で、他店との差別化を図り、「選ばれる店」として生き残るには、戦略的な集客施策が必要不可欠です。

インバウンド需要の増加

新型コロナウイルスの影響で訪日外国人観光客が大幅に減少していた時期を乗り越え、2023年以降はその数が急速に回復しています。観光庁の「インバウンド消費動向調査」によると、2024年7-9月期には訪日外国人の旅行消費額が21,402億円に達し、1人当たりの旅行支出も22.3万円と高い水準を維持しています。
特に、訪日観光客の消費の中で飲食関連の支出は約30%を占めると言われています。これは、飲食店にとって「観光客が日本で食事を楽しむ」という部分がいかに大きなチャンスであるかを示しています。
グラフを見ても、コロナ禍で大幅に落ち込んでいた旅行消費額が、2023年以降で大きく回復していることがわかります。この回復トレンドをうまく取り込むことができれば、新規顧客の獲得はもちろん、リピーターにもつながる可能性があります。
参照元:インバウンド消費動向調査|観光庁
デジタル化の進展
飲食店を取り巻く環境が大きく変化する中、デジタル技術を活用した集客施策がますます重要になっています。特に、業界の競争激化やインバウンド需要の増加に対応するためには、多言語対応のメニューやキャッシュレス決済の導入、SNSやGoogleマップを活用した情報発信が欠かせません。
例えば、多言語対応のメニューは、訪日外国人観光客にとって「安心して食事を楽しめる店」というイメージを与える重要なポイントです。同時に、キャッシュレス決済の導入は、現金文化に慣れていない海外のお客さんにとって利用しやすさを向上させるだけでなく、国内のお客さんにとっても便利な選択肢になります。
飲食店の集客が難しいとされる背景
飲食店の集客が難しいと感じる理由は、一つではありません。前述したとおり、業界全体の環境が大きく変化しており、多くの飲食店が以下のような課題に直面しています。
顧客ニーズの多様化
消費者の価値観やライフスタイルが多様化している中で、飲食店にはそれに対応したサービスやメニューの提供が求められています。「ヘルシー志向」「エシカル消費」「個室での食事」など、個々のニーズが細分化しているため、一つのコンセプトだけではすべてのお客さんを満足させることが難しくなっています。これらのニーズを正確に捉えられないと、集客につながらないことが増えています。
消費者行動の変化
SNSや口コミサイトの普及により、消費者は「行きたいお店」を選ぶ際に事前に情報収集を行うのが当たり前になっています。GoogleマップやInstagram、食べログなどを参考にして来店を決める顧客が多い中で、これらのツールでの情報発信が不足している店舗は、選択肢から外れてしまうことがあります。
コストとリソースの制約
特に中小規模の飲食店では、人手不足に加え、広告予算やスタッフのリソースも限られているため、効果的な集客施策を継続的に実施するのが難しいケースも多くあります。SNS運用や広告出稿には一定の知識と時間が求められますが、日々の店舗運営に追われる中で、そこまで手が回らないという声も少なくありません。
デリバリー業態の広がり
コロナ禍をきっかけに非接触・非来店ニーズが高まり、デリバリー需要が急拡大。デリバリー専門店やゴーストレストラン、間借り店舗などの新業態が広がり、リアル店舗も同じ商圏で顧客を奪い合う状況になりました。利便性や価格、スピードといった競争軸の変化により、従来の集客スタイルだけでは対応しきれなくなっています。
このように、顧客ニーズの多様化や消費者行動の変化、コストの制約が複雑に絡み合う中で、飲食店の集客は以前より難しくなっています。
飲食店の集客を成功に導くためのステップ
飲食店の集客は、やみくもに施策を試すだけでは成果につながりません。顧客ニーズの多様化や限られたリソースの中で集客を成功させるには、流れを意識した取り組みが重要です。以下の3ステップを押さえることで、成果につながる確率が高まります。
1. ターゲット顧客を明確にし、お店のコンセプトを決める
集客のスタート地点は、「どんなお客さんに来てもらいたいのか」を明確にすることです。地域住民、オフィス街のランチ客、観光客、若年層など、ターゲット層によって効果的な施策は異なります。
例えば、地域密着型の店舗では、地元の住民に「家庭的な雰囲気」や「地元食材」を訴求するのが効果的です。一方で、観光客向けの店舗なら、「地元の特色を活かしたメニュー」や「多言語対応」をアピールポイントにすることで選ばれやすくなります。
こうしたターゲットの設定に基づいて、お店のコンセプトを明確にすることが「選ばれる理由」を作り出す第一歩となります。
2. 集客におけるゴールと予算を設定する
集客施策を計画する際には、「どのくらいの予算を使えるのか」という判断基準を明確にしておくことが重要です。この基準を決めるうえでは、まず目標売上と利益を設定し、それに基づいて集客費用の割合を算出する方法が一般的です。
例えば、以下のような基準を参考にすると考えやすくなります。
売上の5~10%を集客予算に充てる
多くの飲食店では、売上の5~10%を集客関連費用に充てるのが一般的です。新規顧客を獲得したい場合や認知度を高めたい場合には、10%を超える投資が必要になることもあります。一方、既存顧客向けの施策では、比較的低コストで成果が得られるため、5%以下に抑えるケースもあります。
目標達成に必要な顧客単価と客数を計算する
たとえば、月間売上の目標が100万円の場合、1人当たりの顧客単価が2,000円であれば、500人の来店が必要です。このとき、新規顧客とリピーターの割合を設定し、それに基づいてどの程度の集客施策が必要かを見極めます。
顧客獲得単価(CPA)を考慮する
集客予算を配分する際には、「1人の新規顧客を獲得するのにいくらかかるのか」というCPA(Cost Per Acquisition)の考え方も重要です。SNS広告の場合、1人あたりのCPAが500~1,000円と仮定すると、50人の新規顧客を獲得するには2.5万~5万円の広告費が必要です。このように具体的な数字を基に計算することで、現実的な予算配分が可能になります。
目標の売上利益率を考慮する
仮に月間利益目標が30万円の場合、そのうち10%を集客予算に割り当てるなら、3万円が目安となります。この予算内で効果的な施策を計画し、リソースを効率よく配分することが求められます。
3. 集客施策の分析や振り返りを必ず行う
どれだけ魅力的な施策を行っても、その結果を振り返り、分析して改善を行わなければ持続的な成功は難しいです。たとえば、SNSの投稿への反応率やGoogleマップの口コミ評価、新規顧客の来店数などを具体的なデータとして把握し、施策の効果を検証しましょう。
振り返りを通じて、「どの施策が効果的だったのか」「どこを改善すべきか」が明確になります。このサイクルを繰り返すことで、集客の精度を高め、持続可能な施策を展開することができます。
お客さんを引き寄せる!飲食店の集客テクニック5選

飲食店が集客を成功させるためには、ターゲットや目的に合わせてさまざまな手法を組み合わせることが重要です。ここでは、実際に活用できる5つの具体的な施策を紹介します。
1:「SNS」で飲食店の魅力を広める
SNSは、飲食店にとって欠かせない集客ツールの一つです。特にInstagramやTikTokは、視覚的な訴求力が高く、店舗の雰囲気や料理の魅力を伝えるのに最適です。
Instagramでは、料理の写真を投稿するだけでなく、「ストーリーズ」や「リール」を活用することで、リアルタイムな情報発信が可能になります。例えば、ランチタイム前に「本日のおすすめ」として、シェフが新作パスタを盛り付けるシーンをストーリーズで公開すれば、視聴者が「今日のランチに行ってみよう」と思うきっかけを作ることができます。また、「リール」で作成したショート動画で、季節限定スイーツの試作風景や、店舗の温かい接客の様子を配信すれば、店舗の個性やこだわりを伝えやすくなります。
TikTokでは、短い動画で楽しい雰囲気を伝えることが鍵となります。たとえば、スタッフが手際よく料理を準備する様子や、人気メニューの「出来立て動画」を投稿することで、ユーザーに「この店を体験したい」という気持ちを抱かせます。また、「お店の1日」として、仕入れから仕込み、営業までをコンパクトにまとめた動画を投稿すれば、店舗の裏側に興味を持つユーザーを惹きつけることができます。
さらに、SNS上でのエンゲージメントを高めるため、ショート動画に「本日限定メニュー」や「○時までのタイムセール情報」を加えることで、来店を促進する工夫も有効です。これらの動画コンテンツは、店舗のフォロワーとの距離感を縮め、リピーターを増やすきっかけにもなります。
2:「Googleマップ」を活用して飲食店を見つけてもら
Googleマップは、今や多くの人が飲食店を探す際に最初に使うツールの一つです。「地元で人気のランチ」や「○○エリア カフェ」などの検索結果で上位に表示されるかどうかが、集客に直結すると言っても過言ではありません。特に、口コミの評価が店舗選びに大きな影響を与えるため、口コミ対応の丁寧さや投稿の充実度が鍵を握ります。
まず、店舗の営業時間、メニュー、写真などの基本情報を正確に登録し、閲覧者にとって分かりやすくすることが第一歩です。また、写真には「どのような特徴があるか」を添えるキャプションを加えると、お客さんが来店後のイメージを具体的に持てるようになります。
口コミの管理も欠かせません。ポジティブなレビューには感謝を伝える返信を心がけ、ネガティブなフィードバックには「申し訳ございません。改善に努めます」といった誠実な姿勢を示すことで、店舗の信頼度を向上させることができます。
さらに、Googleマップ上で季節限定メニューやイベント情報を投稿するなど、最新情報を定期的に更新することで、検索結果での露出が高まり、新規顧客の来店促進につながります。
3:「ポータルサイト」を使って口コミと評価を武器にする
食べログやぐるなび、Rettyといったポータルサイトは、多くのお客さんが来店前に参考にする主要な情報源です。これらのサイトでは、口コミや評価が店舗選びに直結するため、情報を整備することが重要です。
まず、店舗ページには高品質な写真を多数掲載しましょう。料理の写真だけでなく、店内の雰囲気やスタッフの接客風景を加えることで、閲覧者にお店の魅力を視覚的に伝えることができます。また、メニュー情報をしっかり充実させ、主要メニューだけでなく、季節限定やランチセットなどの情報も更新することで、お客さんが来店後のイメージを具体的に持てるようにしましょう。
口コミの管理はGoogleマップと同様に重要です。ポジティブな口コミには感謝を伝え、ネガティブなフィードバックには誠実に対応することで、信頼を築くことができます。さらに、必要に応じて特定のキーワードで上位表示される有料広告を活用することで、新規顧客の獲得を強化するのも効果的です。
ポータルサイトを最大限に活用し、写真やメニュー情報を充実させることで、他店との差別化を図りながら、集客力を高めることができます。
4:「チラシ」や「クーポン」「LINE公式アカウント」で地元住民への効果的なアプローチ
デジタル化が進む中でも、チラシやクーポンは地元住民に直接アプローチできる有効な手段です。チラシでは、季節限定メニューや特典情報を大きく掲載し、QRコードでGoogleマップやLINE公式アカウントに誘導する仕組みを取り入れましょう。
LINE公式アカウントを活用すれば、その場で友達登録を促し、デジタルクーポンを配布することが可能です。「雨の日キャンペーン」や「空席の多い時間帯の割引通知」など、リアルタイムの施策で来店を促進することも効果的です。また、「3回来店でデザート無料」といった継続的な特典を設ければ、リピーターの増加につながります。
5:「イベント」を活用して飲食店への来店動機をつくる
イベントは、新規顧客を引き寄せるだけでなく、お店の認知度を高める効果的な手段です。地域性を活かした「収穫祭」や「マルシェ」への出店は、直接的な利益は少なくとも、お店の宣伝活動として捉えることで、長期的な集客につながります。また、イベント参加者に次回使えるクーポンを配布すれば、リピーター獲得にも効果的です。
店内では、「親子料理教室」や「試食会」といった体験型イベントを企画し、顧客との距離を縮めるのも良い方法です。さらに、近隣の店舗と連携して「パン屋×カフェ」のコラボイベントや「ワインショップ×レストラン」のペアリング講座を開催することで、集客力をさらに高め、地域全体の活性化にもつながります。
イベントは単なる収益活動ではなく、顧客との接点を増やし、店舗のブランド価値を高めるための重要な戦略と考えましょう。
飲食店の集客にはファンを作るブランディングが不可欠!
飲食店の集客を成功させるには、新規顧客を呼び込むだけでなく、「また来たい」「誰かに紹介したい」と思ってもらえるファンを増やすことが大切です。そのために重要なのが、店舗のブランディングです。
ブランディングとは、お店の個性や価値を一貫して伝え、他店と差別化するための戦略です。「地元産の食材を使ったオーガニックカフェ」や「昭和レトロな空間で楽しむ家庭料理」のように、明確なコンセプトを打ち出すことで記憶に残る店舗になります。
料理やサービスだけでなく、内装、接客、SNS発信などにも一貫性を持たせることで、「この店らしさ」が伝わり、ファンづくりにつながります。
ブランディングは単なる集客手段ではなく、長く選ばれる店をつくるための土台です。競争の激しい市場で安定した集客を目指すなら、店舗の価値を明確にし、それを伝え続けることが欠かせません。
飲食店の集客は地道にコツコツ積み上げることが成功への近道
飲食店の集客は、一度に大きな成果を狙うのではなく、小さな努力をコツコツ積み重ねることが成功への近道です。限られたリソースの中でも、SNSでの定期的な投稿、口コミへの丁寧な返信、地域イベントへの参加など、地道な取り組みを続けることで、少しずつ店舗の認知度や信頼を高めていけます。
日々の接客で「また来たい」と思ってもらえる体験を提供し、その積み重ねが口コミやリピーターの増加につながります。集客の結果がすぐに現れなくても、計画を立てて改善を繰り返すことで、小さな成功を積み重ねた先に成果が見えてきます。地道な努力を継続することこそが、飲食店の集客を安定させる鍵です。
飲食店の集客でお困りならtoritokeへご相談ください
SNSやWebサイト運用、チラシ、Googleマップ対策など、飲食店の集客には多くの選択肢があります。とはいえ、「何から始めればいいかわからない」「やってみたけどうまくいかない」と悩まれる方も少なくありません。
株式会社toritokeでは、飲食店の規模や地域性に合わせて無理なく実行できる集客プランをご提案しています。現状の課題整理から施策の実行まで一貫してサポート可能です。
まずはお気軽にご相談ください。あなたのお店の魅力がしっかり伝わる集客の仕組みづくりを、一緒に考えていきましょう。
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

Web集客の関連記事
Web集客とは?53の打ち手と実践のコツ。業界別戦略から費用対効果、ツール活用まで解説
Web集客ツール14選。コスパ重視で実務的なツールを目的別に紹介