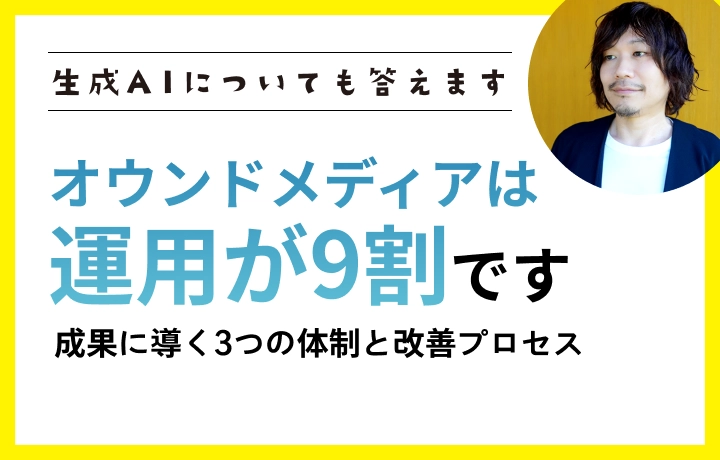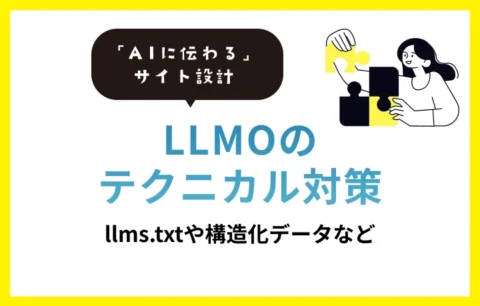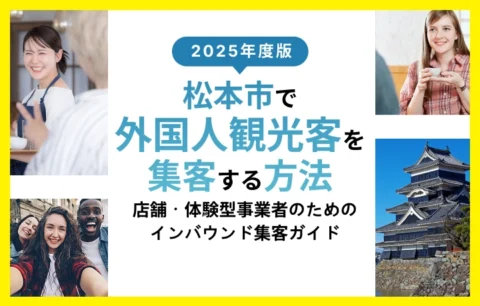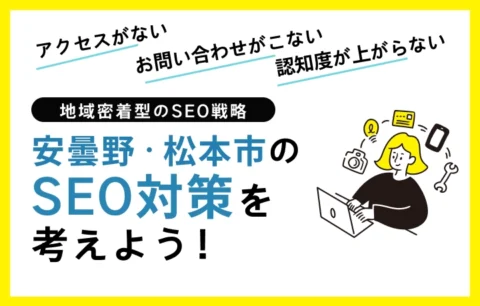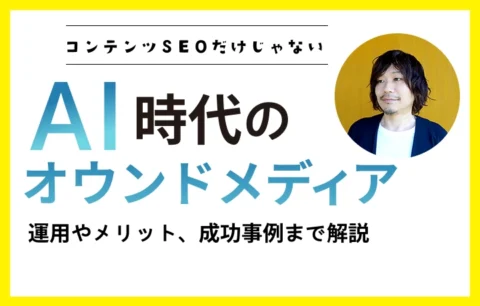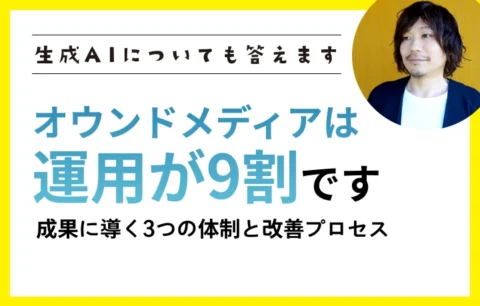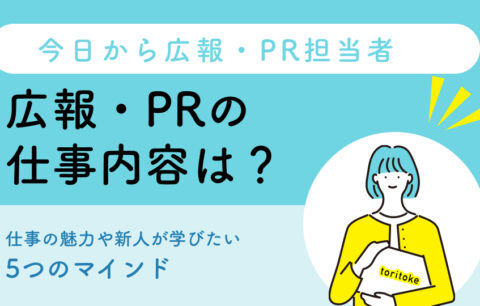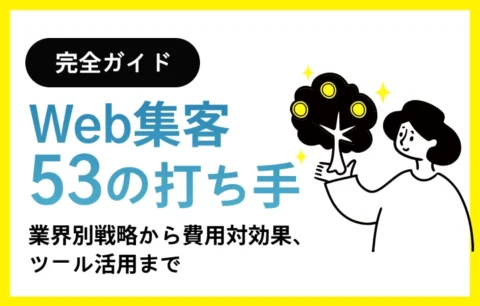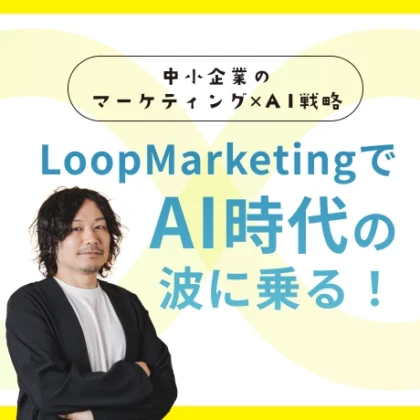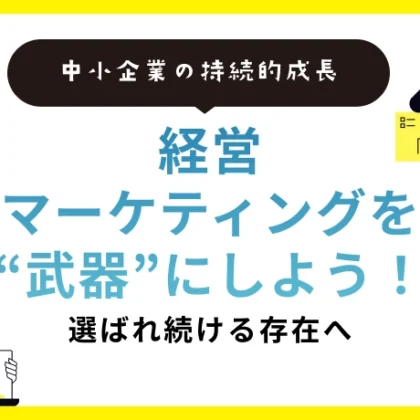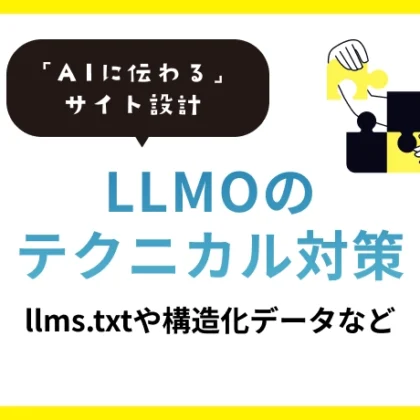「記事を出しても成果が出ない」「忙しくて更新が止まってしまった」そんな悩みを抱えるオウンドメディア担当者は少なくありません。私自身、これまで複数の企業でオウンドメディア運用に携わる中で「成果を左右する決定的な要因は何か?」という問いに何度も向き合ってきました。
SEOに強い構成、SNSで反響を呼ぶ投稿、デザインの工夫…。もちろん、それらも大切です。しかし、最終的に成果を分けるのは“運用体制”と“改善の仕組み”です。
「誰が」「どうやって」「どんなサイクルで」メディアを動かしていくのか。この土台が整っていなければ、どれほど良いコンテンツを作っても、継続的な成果にはつながりません。
この記事では、BtoB・BtoCを問わず、オウンドメディアを“成果の出るメディア”へと育てていくための運用体制、改善プロセス、そして仕組み化の視点について、実践的に解説していきます。
▼この記事の監修者
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

オウンドメディアはなぜ“運用が9割”なのか?
オウンドメディアの成果は、一度の記事や単発の施策だけで得られるものではありません。むしろ、日々の継続的な運用によって信頼が積み重なり、検索流入やリード獲得の基盤が築かれていきます。
構成やデザイン、初期の戦略がどれだけ優れていても、運用が止まれば成果は頭打ちになります。また、しばらく続けてみても目に見える効果が出ず、「この施策は意味がない」と判断されて止まってしまうケースも少なくありません。
実際に多くの企業で、運用がうまくいかなくなる原因は「スキル不足」ではなく「目的の曖昧さ」「体制の未整備」「評価軸の不在」といった設計段階での甘さにあります。つまり、“どう作るか”よりも“どう運用し続けるか”のほうが、成果を左右する決定的なポイントになるのです。
私自身、複数の企業と伴走してきた中で実感しているのは「良い記事があっても成果につながらない」ケースが意外と多いこと。逆に、運用体制や評価の枠組みがしっかり整っている企業では、安定的に成果が積み上がっていく傾向があります。記事やツールの質よりも、“どう動かしていくか”の工夫が成果の差を生み出しているように感じます。
オウンドメディア運用を成功に導く「3つの戦略視点」
オウンドメディアで成果を出すためには、単に「記事を出す」「更新を続ける」だけでは不十分です。運用の土台となる“設計”の部分にどれだけ目を向けられるかが、成功と失敗を分けます。
ここでは、実際の支援現場でも重要視している「3つの視点」をご紹介します。
1. 誰に・何を伝えるのか(発信の軸を定める)
オウンドメディアの成果を左右するのは、記事の内容そのものではなく「誰に向けて」「どんな価値を届けるか」という“発信の軸”の明確さです。この軸があいまいなまま運用を始めてしまうと、コンテンツのトーンやテーマがブレてしまい、読者にとって印象に残らない、いわば誰のためでもない記事になってしまいます。
特にオウンドメディアでは「読まれる」ことが目的ではなく「読んだ人が次のアクションを起こす」ことが目的です。届けるべき相手を具体的に描き、その人の課題に対して、自社ならではの視点でどう応えるかを明確にしておく必要があります。
軸を定める際には、次の3点を具体的に整理しておきましょう。
誰に届けたいのか(ペルソナ)
ペルソナとは「理想の読者像」のことです。年齢や性別、職種などの基本属性だけでなく「どんな立場で、何に困っているのか」「どんな言葉で検索しそうか」など、行動や心理まで踏み込んで想定します。ここが曖昧だと、コンテンツの言葉選びや事例の切り口がぼやけ、誰にも刺さらない記事になりがちです。伝えたい相手を具体化することで、発信の“芯”が生まれます。
例:「従業員10名の製造業を営む40代の社長。技術力には自信があるが、Web経由の新規引き合いが減っており、何をすればいいか悩んでいる。」
相手がどんな課題を抱えているのか
良いコンテンツとは、ただ知識を並べるものではなく相手の“困りごと”に寄り添い、ヒントや気づきを届けられるものです。課題が明確になれば、タイトルの言葉選び、記事構成、事例の出し方など、すべての企画が読者視点に立って設計できます。特にBtoB領域では、検索行動そのものが「課題解決の旅」の途中にあるため、この視点が不可欠です。
例:「問い合わせが減ってきた」「SEOもSNSも試したがうまくいかない」「広告は高くて続けられない」
自社はその課題にどう応えられるのか(提供価値)
オウンドメディアの役割は、単なる情報提供ではなく「なぜその会社に相談するべきか」を伝えることにあります。そのためには、自社の強みや他社との違いを、読者の課題と結びつけて伝える必要があります。ただの営業メッセージではなく、読者の中に「この会社、信頼できそうだな」という感情が芽生えるような情報設計が求められます。
例:「リード獲得につながるコンテンツの設計」「予算を抑えた継続的な情報発信支援」「現場との連携によるBtoBに強いライティング」
このように、誰に何を届けるかという“発信の軸”をしっかり定めておくことで、継続的な記事運用においてもブレがなくなり、成果につながるコンテンツが作りやすくなります。
2. どうやって続けるか(体制・スケジュール・役割分担)
オウンドメディアを「続ける」ことは、一見簡単そうに見えて、実は最も難しい課題のひとつです。多くの企業では、「更新が止まってしまう」「コンテンツの質が落ちてくる」「担当者が離れて誰も手を動かさなくなる」など、運用上の壁にぶつかるケースが少なくありません。
これらの原因は、スキルや知識の不足ではなく、継続できる運用体制と仕組みがないことにあります。どれだけ良い記事を作っても、それを「無理なく回し続ける」仕組みがなければ成果にはつながりません。オウンドメディア運用のためには、以下のような実務的な体制づくりが必要です。
運用に関わる主な役割
- 編集ディレクター:コンテンツ全体の設計・進行管理・品質チェック
- ライター:構成作成・取材・原稿執筆
- デザイナー:アイキャッチ・図解の作成(場合に応じて)
- 社内連携担当:広報・営業・人事など関係部署との情報共有・協力依頼
- 外部パートナー:制作・SEO・分析支援などを担う外注先との連携
続けるための3つの運用ポイント
① 役割の明確化
「誰がネタを出すのか」「誰が書くのか」「誰がチェックするのか」を事前に決めておくことで、属人化やボトルネックを防ぎます。更新が止まる理由の多くは担当が曖昧なことにあります。
② スケジュールの見える化
無理のない更新頻度(例:月2〜3本)を決め、コンテンツカレンダーやタスク管理ツール(Notion、Googleスプレッドシートなど)で進行状況を可視化しておくと、メンバー間の温度差を防ぎやすくなります。
③ 定例ミーティングと振り返り体制
月1回でもよいので、社内やパートナーを交えた定例会を設け、「今月の進捗」「公開記事の反響」「次回のテーマ候補」などを確認・共有する場をつくりましょう。KPIの変化や成果が見えることで、運用の継続モチベーションにもつながります。
内製と外注の“バランス”が継続のカギ
すべてを社内で回す必要はありません。逆に、すべてを外注すると発信に「自社らしさ」がなくなり、読者との距離感が広がってしまうというデメリットも。以下のように切り分けると、効率と効果のバランスが取りやすくなります。
| 項目 | 内製 | 外注 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンテンツの方向性決定 | ◯ | △ | 自社の戦略や価値観に直結するため、社内が中心で設計 |
| 記事執筆(原稿作成) | △ | ◯ | 社内に余裕がない場合はテーマ指示のみで外注に任せることも可能 |
| デザイン制作 | △ | ◯ | テンプレート化できる部分は社内、ビジュアルは外注が安心 |
| 分析・改善提案 | △ | ◯ | SEOやGA4の読み解きなどは、外部の専門家と連携するケースが多い |
| CMS更新・入稿 | ◯ | △ | 慣れれば内製可能。制作初期のみ外部パートナーに委託することも |
成果を出しているオウンドメディアの多くが、このチーム設計と更新の習慣化にしっかりと取り組んでいます。メディアの質を決めるのは、単発の記事の出来よりも、粛々と継続できる地道な設計力なのです。
3. どうやって改善するか(振り返りとKPI設計)
オウンドメディア運用では定期的に効果を振り返り、改善につなげるPDCAサイクルが必要です。毎月記事を更新しているのに、成果につながっていないなら運用方法を見直す必要があります。
改善の起点となるのがKPI(重要業績評価指標)の設定です。例えば以下のような指標がよく使われます。
- •月間PV数(どれくらい見られているか)
- •流入チャネル別の構成(SEO/SNS/指名検索など)
- •指名検索数(ブランド認知の変化)
- •検索順位の推移:狙ったキーワードで何位に表示されているか(SEO施策の成果確認)
- •SNSのシェア数・拡散数:どれだけSNSで共有・言及されているか
- •滞在時間・直帰率(コンテンツの質や導線設計の適切さ)
- •CTAクリック数・CV数(成果に向けたアクション)
- CV数(コンバージョン数):問い合わせや資料DLなど成果につながったアクション数
こうした数値を月次でチェックし、「どんな記事が読まれたのか」「なぜ反応が高かったのか」を分析することで、次に作るコンテンツや改善すべき導線が見えてきます。
さらに、KPIはフェーズに応じて変えていくことも大切です。立ち上げ初期は記事公開数や検索順位の変化、成長期はセッション数やCVといったように、段階に応じて見るべき数値を見極めましょう。

オウンドメディアの効果測定には、以下のようなツールが一般的に活用されます。
⚪︎Googleアナリティクス(GA4)
UU(ユニークユーザー)やPV(ページビュー)、CV(コンバージョン)など、ユーザーの行動や成果指標を多角的に確認できます。
⚪︎Google Search Console
検索クエリごとの掲載順位やクリック数を確認でき、どのキーワードが流入につながっているかの分析に有効です。
⚪︎ahrefs/GRC
狙ったキーワードの順位変動を定点観測できます。SEO対策の効果を中長期で把握したいときに便利です。
⚪︎Looker Studio
GAやサーチコンソールと連携し、成果レポートをダッシュボード化できます。社内共有や定例会での報告資料としても活用されています。
これらのツールを併用することで「どの施策が効いているか」「どこを改善すべきか」といった視点が明確になり、オウンドメディア運用のPDCAをより実践的に回すことが可能になります。

オウンドメディア立ち上げ完全ロードマップ!戦略からKPI、費用相場まで総まとめ
オウンドメディアの成果を高める「定量×定性」視点の改善アプローチ
PVやCVだけでは測れない成果があります。定性指標にも目を向けることで、オウンドメディアの本当の価値と改善のヒントが見えてきます。ここでは定性データの重要性と活用の考え方を紹介します。
オウンドメディアの定性データの種類
オウンドメディアの効果を測るうえで、以下のような定性データが現場でよく活用されます。
- 問い合わせ・商談時に「●●という記事を読みました」と言及がある
- SNSで記事がシェアされ、共感コメントや言及がつく
- 社内で営業資料や提案書に記事が活用されている
- 顧客から「内容がわかりやすかった」「他社より信頼できそう」といった感想が届く
- 社名やブランド名での指名検索が増える
これらは数値としては見えにくいものの、「読まれたその先の行動」や「ブランド理解・信頼構築」に関する重要な手がかりになります。
リードの質から見るキーワードとCVの関係性
CV数だけでコンテンツの効果を評価すると、量はあっても質の高い問い合わせが来ていない…という状態に陥ることがあります。例えば「〇〇とは」のような定義キーワードで流入は多くても、検討フェーズが浅く、商談につながらないケースも多く見られます。
そこで重要なのが、「どんなキーワードで流入してきたか」と「CV後の商談化・成約率の関係性」を定性・定量の両面から分析すること。営業現場と連携し、「このキーワード経由のCVは商談化率が高い」といったフィードバックをもらうことで、より本質的なコンテンツ改善が可能になります。
セールス部門との連携で顧客の真の悩みを探る
セールス部門は、顧客のリアルな声にもっとも近い立場にいます。資料請求や問い合わせのあと、「何を重視しているのか」「なぜこのタイミングで相談したのか」といった生のニーズを直接把握していることが多く、オウンドメディア側で見えていない課題が浮かび上がることもあります。
こうした情報を定期的にヒアリングし、コンテンツの企画やリライトの判断に活かすことで、メディア全体の読者との解像度が高まります。定性視点を活かすには、定期的に部門横断の連携がおすすめです。
オウンドメディア運用でよくある質問
オウンドメディア運用で現場でつまずくよくある質問を紹介します。
Q1. 生成AIでの記事制作が話題ですが、活用しても問題ないのでしょうか?
活用自体は問題ありませんし、実際に多くの企業が活用を始めています。特に記事の構成案やベースとなるたたき台の作成、定型的な説明文の生成などにおいて、生成AIは効率化に貢献してくれます。
しかし「読者の課題に深く寄り添う記事」や「専門性・実体験に基づく内容」では、AIだけで完結するのは難しいのが現状です。読者に信頼される情報として届けるには、ファクトチェックや表現の調整、読みやすさ・分かりやすさを意識した編集が不可欠です。
理想的なのは、AIを補助ツールとして位置づけ、人間が編集・判断の役割を担う運用です。

オウンドメディアとは?AI時代の運用やメリット、成功事例まで解説
Q2. 後発ですが、今からオウンドメディアを始めても成果は出ますか?
十分に成果は狙えます。大事なのは「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にすること。すでに似たような情報が多く存在する中で、後発組に求められるのは、競合と違う視点や深掘りの切り口です。
例えば、特定の業界や職種に向けてピンポイントで課題を扱うニッチ戦略や、社内のリアルな声や独自のノウハウを活かした「現場発信」は、他社には真似できない強みとなります。
スタートの早さよりも、自社らしさをどう活かすかが成果を分けるポイントです。
Q3. 専門的すぎて検索ボリュームがほとんどありません。オウンドメディアでやる意味はありますか?
検索ボリュームが少なくても、質の高い見込み客とつながれるテーマであれば、十分に意味があります。
特にBtoBの領域では、100件の浅いリードより、5件の有望な商談化リードの方がはるかに価値があります。むしろ、専門性の高い分野は競合が少ない場合も多く、正しく届ければ刺さる状態がつくりやすいという利点もあります。
記事を量産するよりも「1本の記事で誰に届けるか」を明確に設計することが、こうした領域では重要になります。
Q4. 費用対効果が合いそうにありません。社内への説明が難しいです。どう伝えればいいでしょうか?
オウンドメディアは、中長期で成果を積み上げていく育成型の施策です。短期間で明確な成果を求められる状況では適さないケースもあります。もし3ヶ月以内に問い合わせやCVを獲得しなければならない状況であれば、リスティング広告やSNS広告など、即効性のある手段に予算を投下した方が合理的です。
しかし、オウンドメディアは広告に比べて費用対効果が出るまでに時間はかかるものの、ストックされたコンテンツで持続的な集客チャネルを構築できるという強みがあります。
社内への説明では、
- 目的が「短期CV」なのか「中長期の集客基盤構築」なのか
- 予算の投下対象としてどの施策がその目的に合っているのか
という「投資判断の軸」を整理することが重要です。

【保存版】オウンドメディアにかかる費用を総まとめ!年間コストと内訳のシミュレーション付
Q5. どのくらいの期間で成果が出ると考えるべきでしょうか?
SEOを主軸としたオウンドメディアであれば、6ヶ月〜1年が一つの目安です。ただしこれはあくまでも目安で、内容の質・更新頻度・テーマ設計の巧拙によって大きく左右されます。
重要なのは、成果が出るまでをただ待つのではなく「成果が出る状態になっているか」を定期的に確認・調整することです。KPIの変化やユーザーの反応を分析しながら、改善サイクルをしっかり回すことで、着実に成果につながっていきます。
運用で差がつくオウンドメディア
オウンドメディアの成果を左右するのは、記事の本数や一時的なPVではありません。本当に重要なのは、「誰に」「何を」「なぜ」届けるのかという設計と、それを支える体制・改善の仕組みが整っているかどうかです。
AIによって誰もがコンテンツを量産できる時代になった今、問われているのは“発信力”ではなく“設計力”。戦略に基づいた企画と運用こそが、成果を生み出す決定的な差になります。
株式会社toritokeでは、オウンドメディアの立ち上げから運用まで一貫して対応しています
オウンドメディアで成果を上げるには、立ち上げ時の設計だけでなく、その後の運用と改善をいかに継続できるかが重要です。株式会社toritokeでは、戦略設計から記事制作、体制構築、KPI分析・改善提案までを一貫して支援しています。
- 「何を書けばいいかわからない」
- 「記事は出しているけれど、成果が見えない」
- 「運用が属人化していて止まりがち」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。現状の整理から、無理のない改善ステップまで、貴社の課題とリソースに合わせた最適な運用設計をご提案します。
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー