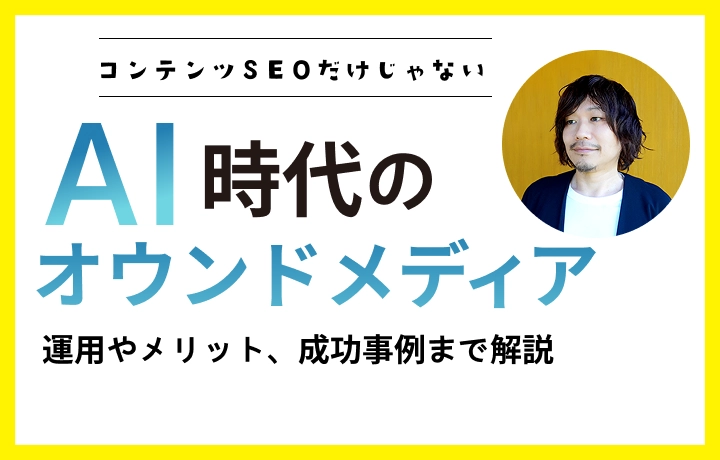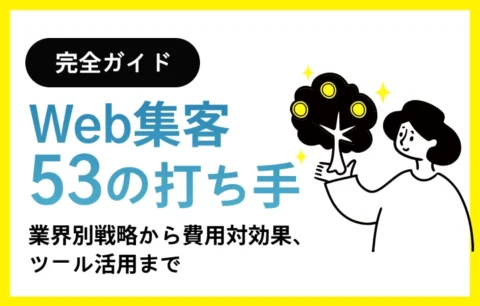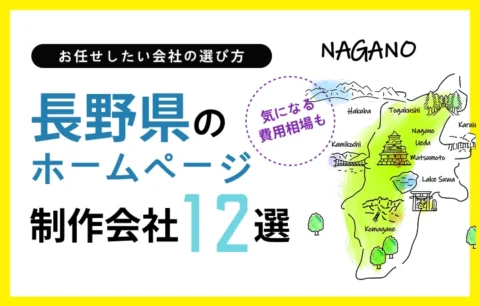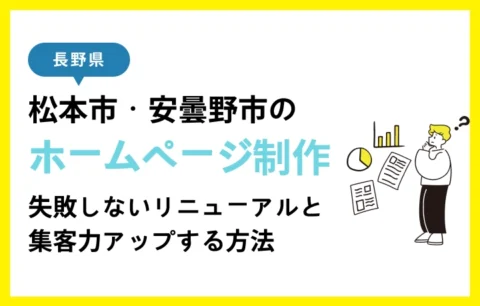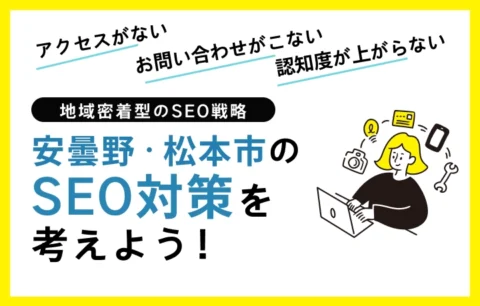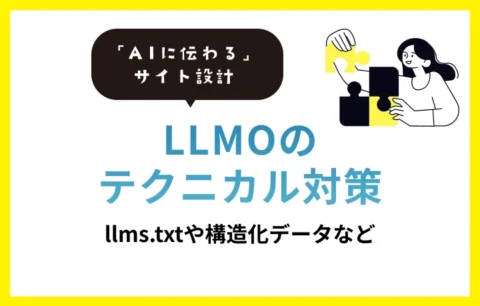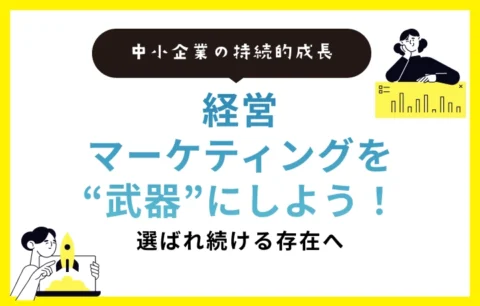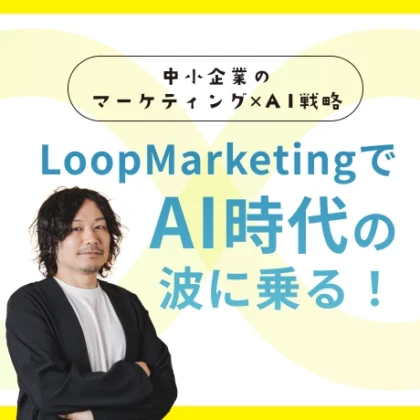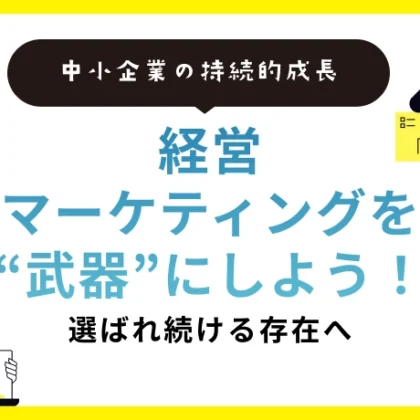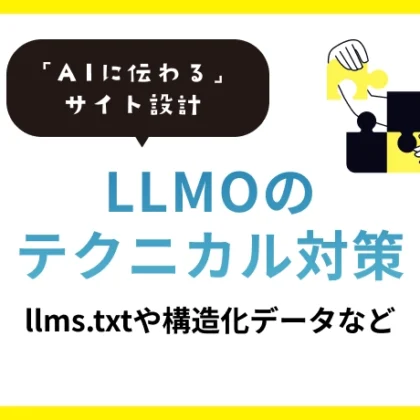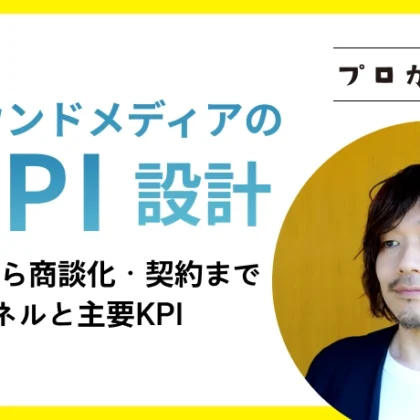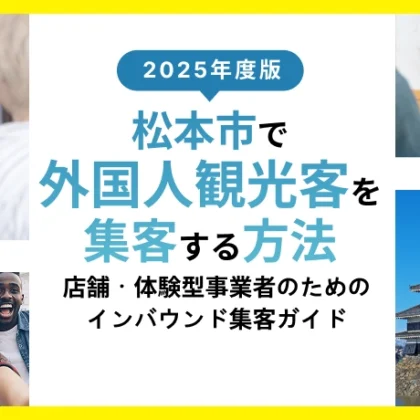オウンドメディアは、検索エンジンやSNSのアルゴリズムに左右されず、自社の資産として情報発信ができる“土台”です。特にAI検索が普及しつつある今、自社の信頼性や専門性を蓄積できるオウンドメディアの重要性はさらに増しています。ただし、続ければ成果が出るというものではなく、目的設計・体制・KPI設計・継続性があってこそ価値が生まれます。
この記事では、オウンドメディアの定義やメリット・デメリットから、立ち上げ方法、費用感、運用のコツ、KPI設計、成功事例まで幅広く解説します。
▼この記事の監修者
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

オウンドメディアとは?
オウンドメディアとは、企業や個人が自ら所有・運営する情報発信メディアのことを指します。具体的には、コーポレートサイト内のブログ、ブランドサイト、採用サイト、メールマガジン、note、YouTubeチャンネルなどが該当します。
SNSや広告と異なり、プラットフォームの制限を受けずに、自社の方針や目的に沿ってコンテンツを発信できるのが特徴です。また、発信したコンテンツが蓄積されていくことで、資産として価値を持つ点も大きな魅力です。
そして今、検索エンジンに加えて生成AIが信頼できる情報源をもとに回答を生成するようになったことから、企業の公式な情報発信チャネルであるオウンドメディアが、より重視される傾向にあります。
オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディアの違い
マーケティングでは、情報発信のチャネルを「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」の3つに分類する考え方があります。
| メディアの種類 | 概要 | 主な例 |
|---|---|---|
| オウンドメディア | 自社が保有・運営するメディア | コーポレートサイト、ブログ、note、YouTubeなど |
| ペイドメディア | お金を払って掲載するメディア | リスティング広告、SNS広告、Web広告など |
| アーンドメディア | 第三者に紹介・拡散されるメディア | SNSでの口コミ、レビューサイト、メディア掲載など |
オウンドメディアは、自社で発信の主導権を握れるのが強みですが、拡散力ではアーンドメディアや即効性のあるペイドメディアと組み合わせることで、効果を高めることができます。
オウンドメディアのメリット・デメリット
オウンドメディアは、中長期で成果を生む“資産型”のマーケティング施策です。即効性はありませんが、うまく運用すれば広告に頼らず集客や信頼構築ができる仕組みをつくることができます。ただし、運用には一定の準備・体制・視点が求められるため、立ち上げ前にメリット・デメリットの両面を理解しておくことが大切です。
オウンドメディアに投資するメリット
長期的な資産になる
一度発信したコンテンツは、継続的にアクセスされる可能性があります。たとえば、検索ニーズのある内容を記事化しておけば、広告のように出稿をやめた途端に消えるのではなく、自然検索などから“継続的に流入が見込める状態”をつくれます。
情報を自由にコントロールできる
SNSや広告は表示形式やアルゴリズムに制限されますが、オウンドメディアなら、伝えたい順番や表現を、自社の意図通りに設計できます。たとえば、事業の背景や担当者の想いなど、ストーリー性のある内容も自由に掲載可能です。
他チャネルと連携しやすい
作成した記事や動画は、SNS・広告・営業資料・セミナーなど、さまざまな場所で再利用できます。Web集客の軸を一本つくることで、施策同士の連携もスムーズになります。
自社の専門性や信頼性を積み上げられる
継続的に情報を発信することで、「この分野に詳しい会社」「信頼できる企業」と認知されやすくなります。特に専門性や実績を可視化することで、指名検索や口コミにつながるケースも増えていきます。
オウンドメディアに投資するデメリット
成果が出るまでに時間がかかる
コンテンツを公開しても、すぐに検索結果に反映されるわけではありません。Googleなどの検索エンジンに評価されるまでには、数ヶ月〜半年以上かかることもあります。短期的にリードを獲得したい場合には不向きです。
運用には継続的なリソースが必要
記事の企画・執筆・校正・公開・効果検証といった一連の流れを、定期的に回し続ける体制を社内で持つか、外部パートナーと連携する必要があります。単発ではなく、継続できる体制設計が鍵です。
目的が曖昧なままだと形骸化しやすい
「とにかく毎週更新」だけが目的になってしまうと、誰のための記事なのかが曖昧になり、読まれずに終わるケースも多いです。オウンドメディアは“メディア”である以上、ターゲットや目的を明確にしないと、続ける意味を見失ってしまいます。
オウンドメディアの課題
オウンドメディアは、広告に頼らず自社の価値を発信できる強力な手段ですが、継続・成果の可視化・社内連携といった運用面の難しさに加え、AI時代ならではの新たな課題も浮上しています。ここでは、現場でよく直面する4つの課題を紹介します。
継続できない
オウンドメディアは“立ち上げよりも継続”が難しい施策です。はじめは社内で盛り上がっていても、数ヶ月後には更新が止まってしまうケースが少なくありません。
- 担当者が兼任で時間を確保できない
- ネタが枯渇して「何を書けばいいかわからない」
- 効果が見えず、モチベーションが続かない
- 一部の人に負荷が集中し、運用が属人化する
継続には、無理のないペースと、チームで分担する仕組みが必要です。
効果が見えにくい
成果が出るまでに時間がかかるのがオウンドメディアの特徴です。検索順位が上がっても、問い合わせに直結しないと「意味がない」と判断されてしまうこともあります。
- 記事は読まれているが行動につながらない
- 数字だけを見ると“反応がないように見える”
- 成果をどう測ればいいかわからない
- 社内での評価や理解が得にくい
効果を見える化するには、アクセス数や検索順位だけでなく、ブランド認知や再訪率なども指標として持つとよいでしょう。
社内との連携がうまくいかない
良いコンテンツは、社内の知見や顧客情報があってこそ成り立ちますが、実際には部門を超えた連携がうまくいかず、素材が集まらないこともあります。
- 営業や開発に情報提供を頼みにくい
- 原稿の確認・承認フローが煩雑
- 「なぜ発信するのか」が現場に伝わっていない
- 情報共有がメールやチャットで断片的
コンテンツを「会社全体でつくるもの」と捉える視点が、円滑な連携の第一歩です。
AI検索時代における信頼構築の難しさ
ChatGPTやGoogle Geminiなどの登場により、検索結果の表示だけでなく「誰の情報を引用するか」が重要になっています。従来のSEOだけでは、信頼される情報源にはなりにくくなっています。
- AIが参照しやすい構造になっていない
- 企業や著者の信頼性が明示されていない
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)への配慮が不足
- 記事の中で主張と根拠の関係が曖昧
AIにも“選ばれるメディア”になるためには、情報の質だけでなく、誰がどんな背景で発信しているのかを明確に示す工夫が必要です。
オウンドメディアを立ち上げるには?準備すべきこと
オウンドメディアは、なんとなく始めてもうまくいくものではありません。立ち上げ直後こそモチベーションが高くても、目的や体制、発信内容の方針が曖昧なままでは、すぐに手が止まり、社内からも「続ける意味があるのか?」と疑問の声が上がりがちです。
だからこそ、運用をスタートする前に「何のために」「誰に向けて」「どのように」発信していくのかを、あらかじめ明確に設計しておくことが欠かせません。企業の価値や強みを言葉にして伝える場だからこそ、立ち上げ段階での設計がその後の成否を大きく左右します。
立ち上げ前に整理しておきたいポイント
- 目的の明確化(例:集客/採用/ブランディング など)
- ターゲット設定(誰に向けて情報を届けるのか)
- 投資計画の検討(初期設計・制作・運用にかかる費用と予算配分)
- 発信テーマと方針の決定(情報の軸とトーンの統一)
- 更新体制の構築(役割分担と現実的なスケジュールの設計)
- 社内ルールの整備(原稿確認・承認・公開までのフロー)
- 必要に応じた外部パートナーの検討(制作・運用・分析の外注も視野に)
こうした準備を丁寧に進めておくことで、立ち上げ後の運用が格段にスムーズになります。やるべきことが整理され、関係者との連携も取りやすくなるため、更新の手間やストレスを減らせるだけでなく、「ネタがない」「忙しくて止まってしまった」といったよくあるつまずきを未然に防ぐことができます。
さらに、目的に沿ったコンテンツが継続的に蓄積されることで、社内外にとって意味のあるメディアとして育ち、企業の資産として価値を発揮するようになります。

オウンドメディア立ち上げ完全ロードマップ!戦略からKPI、費用相場まで総まとめ
オウンドメディアにかかる費用はどれくらい?内製・外注の考え方と費用感の目安
オウンドメディアは「無料で始められる」と思われがちですが、実際には立ち上げの設計や記事制作、日々の運用管理に至るまで、一定の費用や人的工数がかかる施策です。特に、明確な成果を求める場合には、継続的な投資とリソース配分を前提とした計画が必要になります。
主な費用項目と費用相場
- 初期設計費用:10万〜50万円前後(戦略立案/コンセプト設計/構成案の策定など)
- CMS構築費用:20万〜100万円前後(WordPressやヘッドレスCMSの導入・デザイン・カスタマイズ)
- 記事制作費用:1本あたり3万〜10万円前後(取材・ライティング・校正・画像制作など)
- ディレクション・編集費用:月額5万〜20万円前後(進行管理・品質管理・スケジュール調整など)
- 分析・改善ツール費用:月額0〜5万円前後(Google Analytics、Search Consoleは無料。有料SEO・ヒートマップツール等)
- 継続運用にかかる外注費:月額10万〜50万円以上(記事更新、レポート作成、改善提案、編集支援など)
どこまでを内製でまかなうか、どこを外部パートナーに任せるかによって、コスト感は大きく変わります。加えて、発注先の規模(大手制作会社・中小規模の制作会社・個人フリーランスなど)によっても、クオリティの安定性やサービスの範囲、対応スピードに差が出るため、自社の方針や体制に合ったパートナー選定が重要になります。
内製と外注、どう切り分ける?
費用を抑えようとしてすべてを内製しようとすると、担当者の負担が増えすぎて継続が難しくなることがよくあります。一方で、すべてを外注に任せると、発信の中身が自社らしさに欠け、ブランドとのズレが生じるリスクも。以下のような基準で、社内と外部の分担を整理しておくのが現実的です。
社内で担いやすいもの
- コンテンツの企画立案
- 発信テーマの選定
- 商品・サービスに関する一次情報の提供
- 専門知識や顧客課題の共有
- 自社らしい表現・トーンの定義
- 社員インタビュー・事例収集
- 営業・CS部門からのネタ出し
- Googleアナリティクスの簡易チェック(PV、CVなど)
外部に任せやすいもの
- CMSの構築・改修
- 記事の構成設計・リライト・校正
- SEO記事やホワイトペーパーの執筆代行
- アイキャッチや図解などのデザイン制作
- 効果測定・レポート作成(GA4・ヒートマップ分析など)
- KPIに基づく改善提案・数値分析サポート
- 記事更新・管理の代行
- SNSやメルマガの運用支援
ポイントは、社内にしか出せない情報や価値は内部で確保しつつ、専門スキルや負荷が大きい部分は外部に任せて継続性と品質を担保することです。

【保存版】オウンドメディアにかかる費用を総まとめ!年間コストと内訳のシミュレーション付
オウンドメディアの運用で押さえるべきポイント
オウンドメディアは立ち上げて終わりではなく、“運用して育てていく”ことこそが成果に直結する本質的なフェーズです。コンテンツの更新、効果測定、改善のサイクルを継続して回す体制が求められます。
社内でリソースを確保するのが難しい場合は、編集・制作・レポート作成など一部の工程を外部に委託し、負担を分散させながら継続できる仕組みをつくることが重要です。
運用で押さえておきたい基本の業務フロー
- 月次または四半期単位での編集会議(企画出し・優先度整理)
- コンテンツ制作(ライティング・校正・公開作業)
- 効果測定(PV・CV・滞在時間など)
- 定期的な振り返りと改善案の検討
- 社内フィードバックの取り込み・共有
- SNSやメルマガなど外部チャネルとの連携
オウンドメディアは「つくる」ことよりも、「続ける」ことのほうがはるかに難易度が高く、社内の温度差や属人化によって頓挫するケースも少なくありません。誰が、どの役割で、どのくらいの頻度で運用するのかをあらかじめ決めておくことで、安定した更新・改善サイクルを維持しやすくなります。

オウンドメディアは運用が9割!成果に導く3つの体制と改善プロセス
オウンドメディアのKPI設計|フェーズに応じた指標の考え方
オウンドメディアの成果は、立ち上げてすぐには見えにくいものです。フェーズごとに「何を目指すのか」を明確にし、それに応じたKPIを設計しておくことで、運用の軸がブレずに進めやすくなります。ここでは、オウンドメディアの成長段階に応じて追うべき指標と、その背景にある考え方を紹介します。
【フェーズ1】立ち上げ期(運用開始〜6ヶ月)
目的:サイトの土台づくりと投稿習慣の確立
- 記事公開数(月2〜4本が目安)
- PV(ページビュー):まずは月1,000PV程度を目標に
- 検索インデックス数(Googleに正しく登録されているか)
- 流入チャネル別のアクセス数(検索/SNS/ダイレクトなど)
この時期は、数値目標よりも「継続できる体制づくり」に重きを置くことが重要です。どれだけ戦略やKPIを設定しても、コンテンツが更新されなければメディアは育ちません。月2〜4本など、現実的に投稿できるペースを定め、無理のないスケジュールを整えることが成果への第一歩です。
また、記事制作や承認フローなどの運用ルールを社内に根づかせることも欠かせません。投稿を特別な施策ではなく日常の業務として扱えるようになることで、露出のベースが整い、次のフェーズへ進みやすくなります。
【フェーズ2】成長期(運用開始6ヶ月〜1年)
目的:検索流入の拡大と行動導線の整備
- UU(ユニークユーザー):月1,000〜5,000UUを目安に
- 検索順位(主要キーワードでの順位推移)
- 平均滞在時間(1分以上)、直帰率(60%以下を目安に)
- CTAクリック数(資料請求・問い合わせなどへの誘導)
立ち上げ期を終えると、いよいよコンテンツの「質」と「成果」が問われてきます。検索ニーズに合ったテーマ設計や、見出し・構成の工夫が求められ、ユーザーがどこから来て、どこで離脱しているのかを数値で把握することが重要です。
加えて、問い合わせや資料請求など、次のアクションにつながるCTAの設計・配置もポイントとなります。記事の公開にとどまらず、メディア全体で「目的地」まで導けるように整備していく段階です。
【フェーズ3】成果創出期(運用開始1年〜)
目的:成果の最大化と信頼の蓄積
- CV数(問い合わせ/資料請求/説明会申込など)
- CVR(コンバージョン率):1〜3%を目安に
- 指名検索数(ブランド名での流入)
- リピーター率・SNSでの言及数・間接効果(他施策との連携)
1年を超えてくると、単なるアクセスの多寡よりも「どれだけ成果につながったか」が指標になります。ここでは、CV数やCVRなどの定量指標に加え、ブランド名で検索される「指名検索数」や、SNSでのポジティブな言及など、信頼や認知の蓄積を測る視点も加わってきます。
また、広告やイベントなど他チャネルとの連携を通じて、「間接的にオウンドメディアがどのように機能しているか」までを視野に入れた運用が求められる段階です。
【フェーズ4】再設計・連携強化期(2年〜)
目的:既存資産の見直しとマーケティング全体との接続
- 検索順位・流入の鈍化(過去記事の鮮度・競合の台頭)
- コンテンツテーマの広がりすぎ・重複
- MA・CRMとの連携精度(シナリオ連携・セグメント別反応)
- リピーター比率やコンバージョン経路の複雑化
長く運用を続けたオウンドメディアでは、「記事がある程度出揃った」状態からの進化が求められます。このフェーズでは、コンテンツの“再整理”と“他チャネルとの連携強化”が大きなテーマになります。特に、MA(マーケティングオートメーション)やCRMとの接続を強化することで、オウンドメディアをリードナーチャリングや商談化の導線に組み込む動きが重要になります。
- メルマガのクリック率や配信結果から、反応が良い記事傾向を分析
- CRM上の見込み客データをもとに、関心テーマ別の記事をレコメンド
- ホワイトペーパーや事例コンテンツを、営業プロセスに自然に組み込む
- MAの閲覧履歴を活かした記事の出し分けや自動ステップ配信の構築
マーケティング全体と連携する情報基盤(コンテンツハブ)として機能させることが、次の成長フェーズにつながります。

オウンドメディアのKPI設計を戦略的に!CVから商談化・契約までつなげるファネルと主要KPI
オウンドメディアの成功事例
オウンドメディアの効果は、企業の業種や課題によって現れ方が異なります。ここでは、toritokeが支援した中から代表的な2つの事例を紹介します。自社の立ち上げや改善のヒントとして、ぜひご活用ください。
BtoB企業の事例|リード獲得から案件化までを仕組み化

企業向け研修サービスのオウンドメディア活用
紹介や既存顧客に依存していた営業体制を脱却し、検索経由での新規リード獲得からナーチャリングによる案件化までを一貫して実現したBtoB企業の事例です。
これまでは、限られた人的リソースの中で紹介対応や受注フォローに追われ、営業の間口を広げる施策に着手できていませんでした。また、Webサイトは「名刺代わり」としての役割にとどまり、検索からの流入やリード獲得の導線が整備されていない状態でした。
そこで導入したのが、コンテンツマーケティングとHubSpotを軸としたマーケティング体制の再構築です。まずは、ニーズが顕在化していない潜在層にもアプローチするため、SEOを意識した記事コンテンツを月3本ペースで制作。ユーザーの課題をテーマに据えた「読み物型コンテンツ」によって、少しずつ検索経由の流入と指名検索数を伸ばしていきました。
あわせて、研修検討フェーズの顧客向けにホワイトペーパーを複数本制作し、“読む→ダウンロード→ステップメール→案件化”の仕組みを構築。HubSpot上でリード情報を一元管理し、メール配信やステータス変更などを可視化・自動化することで、営業担当者の負担を最小限に抑えながらも、質の高い見込み客との接点を維持できるようになりました。
その結果、属人的だった営業プロセスが「仕組み化」され、受注確度の高い問い合わせが継続的に創出される体制が整ったのです。

【企業向け研修】コンテンツマーケティング×CRMでリード獲得から案件化まで仕組みを構築
地域密着型企業の事例|自然検索流入と問い合わせを安定化

建築・施工業のコラム型SEO戦略による中長期施策の成果
これまでInstagramや紙チラシを中心に集客を行ってきた地域密着型の建築会社において、広告依存から脱却し、検索経由での問い合わせを安定的に得られる状態をつくることを目的に、オウンドメディアを立ち上げた事例です。
同社は、個人住宅の施主や法人の施設担当者など、多様なターゲットを抱えており、比較検討の際には「まずネットで調べる」傾向が強いことが分かっていました。しかし、これまでのサイトには十分な情報量がなく、Google検索で選ばれる導線が欠如している状態でした。
そこで、ユーザーの検討フェーズに合わせたSEOキーワード設計を実施し、「基礎知識」から「比較ポイント」「費用の目安」「施工の流れ」など、段階に応じたコンテンツを体系的に整備。月3本のペースでコラム型記事を更新し、Webサイトを“情報提供のハブ”として機能させることを目指しました。
さらに、施工事例ページとの内部リンク設計を強化し、「読み物→事例→問い合わせ」と自然に誘導できるサイト構造に再設計。記事の末尾にはFAQやCTAボタンを設置し、読み終えたユーザーが次の行動に移りやすい構成としました。
この結果、自然検索からの月間流入は施策開始から半年で約2倍に増加。問い合わせ数も右肩上がりで推移し、短期的な広告ではなく、資産として蓄積される集客基盤として機能し始めています。

【建築・施工】オウンドメディア運用で自然検索流入と問い合わせが着実に増加
オウンドメディアは、企業の“想い”を伝えるメディア
オウンドメディアは、単なる集客チャネルやSEO施策としてだけでなく、自社の理念や価値観、こだわり、これからの姿勢を伝える場として大きな意味を持ちます。
特にAIがコンテンツを生み出す時代においては、どの企業がどんな意図で発信しているのかという「文脈」や「信頼性」が、これまで以上に重要視されるようになっています。
そして、記事を書くだけでは成果にはつながりません。SEO、SNS、広告、ホワイトペーパー、メルマガ、動画といった複数の施策と連携しながら発信していく、まさに“AI時代のマーケティングにおける総合格闘技”ともいえる存在がオウンドメディアです。
テクニックだけでは勝てない時代だからこそ、「どんな会社が、どんな想いで」発信しているのかが、選ばれる理由になります。企業の言葉と姿勢を伝え、顧客と信頼関係を築いていく手段として、オウンドメディアは今後ますます重要性を増していくでしょう。
株式会社toritokeでは、オウンドメディアの立ち上げ・運用をご支援しています
オウンドメディアは、始めることよりも「続けること」、そして「成果につなげること」が何よりも難しい施策です。目的設計から記事制作、分析・改善まで、限られたリソースの中でやりきるには、無理のない設計とパートナーの伴走が欠かせません。
株式会社toritokeでは、中小企業や個人店舗、新規事業者向けに、オウンドメディアの戦略立案から運用体制づくり、継続的な改善支援までを一貫してサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」「続ける仕組みを整えたい」「もっと成果につなげたい」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- ●
予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●
顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●
現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー